���������ʥ
- ���Υե������˿������ȥԥå���Ω�Ƥ뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- ���Υե������Ǥϥ�������Ƥ��ػߤ���Ƥ��ޤ�
inomaty
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
����Ф�ϡ�inomaty�Ǥ���
�����ޤ����Ѥ��������ʥ�����ȥԥå��Ǵ��������ʥ��������ޤ����ȴ������ѤǤ��������줳���ǥ�������֤��ޤ����Ȥʤ���̤����ƤǤ��Τǿ����˥ȥԥå���Ω���夲�ޤ�����
�Ȥꤢ�������������ʥ�Υ���������ɤϤ����颭����
https://github.com/inomaty/Kansai-fg-CustomScenery
�ǽ�˥ͥ��ߤ����ʤ�κ�äƿ������ʤ��Ǥ����ɡ������⤬����褦�ʶ��������Ϥˤ���������Ǥ���

�����Ҳ𤷤����֥�å������ʥ�ˤ��뼫ư�ǥǥ��������Ƥ���륷���ƥ�˺��ޤ�����YAsim�ΥХ��ǥѡ����֥졼���Ƥ��Ƥ�ɤ����Ƥ���̯�˰�ư���Ƥ��ޤ��Τǡ����������濴�ˤ����Τ˺Ǹ�ˤϤ��ʤꥺ�줿���֤ˤʤäƤ��ޤ��Τ������Ǥ���HiTouch���������SH-60J�����ι�碌�ƥѡ��ƥ������ߤ��褦�ˤ��Ƥޤ��������Τ��⳰��Ƚ���̵���Τǿ��夷�ޤ��������Τ����ALS�α����ߤä����˿�ũ���դ���ǽ����ܤ��Ƥ��Ƥ������ط�̵���褦�Ǥ���
�ܲ�Wiki��particle system�Υڡ������CPU����٤��빽�ݤ��륷���ƥ�Τ褦�ǡ�����Ū�˼꤬����褦�Ǥ������ʮ�ͤ��亮�ߥ�졼����Ƥ���Τ��ϼ��PC�Ǥ��ȿɤ����⤷��ޤ���
����ޥ���ץ쥤�䡼���Ǥ�ȯư���ޤ���

�����ޤ����Ѥ��������ʥ�����ȥԥå��Ǵ��������ʥ��������ޤ����ȴ������ѤǤ��������줳���ǥ�������֤��ޤ����Ȥʤ���̤����ƤǤ��Τǿ����˥ȥԥå���Ω���夲�ޤ�����
�Ȥꤢ�������������ʥ�Υ���������ɤϤ����颭����
https://github.com/inomaty/Kansai-fg-CustomScenery
�ǽ�˥ͥ��ߤ����ʤ�κ�äƿ������ʤ��Ǥ����ɡ������⤬����褦�ʶ��������Ϥˤ���������Ǥ���

�����Ҳ𤷤����֥�å������ʥ�ˤ��뼫ư�ǥǥ��������Ƥ���륷���ƥ�˺��ޤ�����YAsim�ΥХ��ǥѡ����֥졼���Ƥ��Ƥ�ɤ����Ƥ���̯�˰�ư���Ƥ��ޤ��Τǡ����������濴�ˤ����Τ˺Ǹ�ˤϤ��ʤꥺ�줿���֤ˤʤäƤ��ޤ��Τ������Ǥ���HiTouch���������SH-60J�����ι�碌�ƥѡ��ƥ������ߤ��褦�ˤ��Ƥޤ��������Τ��⳰��Ƚ���̵���Τǿ��夷�ޤ��������Τ����ALS�α����ߤä����˿�ũ���դ���ǽ����ܤ��Ƥ��Ƥ������ط�̵���褦�Ǥ���
�ܲ�Wiki��particle system�Υڡ������CPU����٤��빽�ݤ��륷���ƥ�Τ褦�ǡ�����Ū�˼꤬����褦�Ǥ������ʮ�ͤ��亮�ߥ�졼����Ƥ���Τ��ϼ��PC�Ǥ��ȿɤ����⤷��ޤ���
����ޥ���ץ쥤�䡼���Ǥ�ȯư���ޤ���

--
OS:Win7 Pro 64bit
�� Ubuntu14.04LTS
FG version:Win7:3.4,2017.3.1
���������� Ubuntu:2016.1.1,2016.2.0
��ɼ��:21
ʿ����:4.76
hide
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
��hide�Ǥ�������Ʋ����פǤ��Τ餻���ޤ����̤ꡢinomaty����Ρֿ����ޤ����Ѥ��������ʥ����פα����ԤȤ��ơ����������Ω���ϡ��ʤޤ����ޡˤˤ�����إ�ݡ��ȡפ��ǥ벽���ޤ��������礦�ɿ������ȥԥå���Ω�Ƥ�ĺ�����Τǡ�������Ϥ����ޤ���
���إ�ݡ��Ȥ����Ǥϼ䤷���Τǡ��������ˤ����åȥϡ��С���¤�äƤ��ޤ��ޤ����������ˤϡ���90��������Ω�ɤʥ���åס�����Φ�Ȥ����뷹��ϩ�ˤ����äơ��������ۤ�ˤ䤫�ˤ���С���嵡����������ȯ�ʡ����Ƥˤ�äƤ����Ǥ��������dz��Ѥϥ�åȥϡ��С��ΤޤޡʲͶ��δ�������Ǽ�ˤϺ�餺�ˡ��Ͼ�ǵ��Τ�ư��ǽ�ˤ��ơ���嵡���Ϥ˻Ȥ���褦�ˤ��ޤ�����
���ޤ����إ�ݡ�����¦���Ӥζ���̿��Ƥ����顢�Ͼ��������������ϩ�Ȥ����פ��ʤ��������Ƥ�ȯ�����ޤ������¤Ϥ��������Ω���Ϥϡ�2008ǯ���ؤ�Ͷ�פ��ᥤ����ˤ���Ϥ����ä����Ǥ������δط��ǡ������Ծ�פ����ߤ��줿��ΤΡ����س��Ť��̵��˼��줿�塢���٤Ⳬ�����ʤ��ޤ�������ĤĤ���褦�Ǥ������ߡ������ϩ����ü�ն�ϥ����ȥ���������ü�ϥ��饦��ɡ���¦�ϥ����ȥ�����ʤɤˤʤäƤ��ޤ�����ä����ʤ��Τdz���ϩ��ͶƳϩ��Ƹ����ơ�������٤�褦�ˤ��ޤ�����
���Ȥ�������ǡĵ����դ��С��鷺��������ľ����ˡ����Ĥμ������Ծ졦�إ�ݡ��Ȥ��¤֤��Ȥˤʤ�ޤ�����
�����ޤ����إ�ݡ��Ȥ�¤�롧
����������˥إ�ݡ��Ȥ�������Τϡ�������ꤺ�äȾ���������ץ�ʤΤǡ���ˤ����������Ȼפä�����Ǥ���
��3ǯ�����إꥳ�ץ�����Ǯ�椷�ơ��ٻλ�ĺ�ؤΥ�ɡ����ߤ�夲�Ƹ��ե饤�Ȥʤɤ�ֳƼ�����ˤĤ��ơץե�������Ϣ�ܡּ�õ���ˡ��ι�����סʤ��Σ��ˤǤ��Ҳ𤷤��������֥إꥳ�ץ�����Ĥ�ABC�סʥ�������MOOK��2000�ߡˤȤ����ܤ��ɤߡ������إ�ݡ��Ȥ�¸�ߤ��Τ�ޤ��������ͣ��θ����إ�ݡ��Ȥǡ�ǯ����Φ���������إ�ݡ��Ȥ˼�������2�̤��Ȥ��������ʥ����ߥʥ�ӥ�˵ձ߿����δ��������������ǥ��������ơ����Һ�äƤߤ����ʤ�ޤ�����
���ޤ���������Ǥ������إ�ѥåɤΰ��֤䥵���������̡�ɸ��ʤɤϥͥåȤǤ���Ƚ�����ޤ������������Τβ�����ɬ�פǤ������������ʤ�ܤ���ʿ�̿ޤ���ɽ����Ƥ��ޤ����ۤ��˸��Ϥμ̿��줳�������GoogleEarth��������ơ����̥����å����ʪ�κ����˻Ȥ��ޤ�����������GoogleEarth�ο����ο��������դǡ����ä����߸Ϥ�β��������ޤ��ȡ������ʤʹӤ��ϤˤʤäƤ��ޤ��ޤ��������Ͽ��Ф䡢����ε���ͤˤ�������ΤǤ��͡�
������WED��ư���ơ������ˡ�Maishima�פȤ����ե�������äƵ�ư����˥塼�С������Create Airport�פ����ơ�̾�Τ��[H]Maishima Heliport�פȤ��ޤ��������¤��إ�ݡ��Ȥ�ICAO�����ɤ��դ��Ƥ��ʤ��ΤǤ�����������ص����RJH01�פȤ��ޤ�������Ǥ��ä������嵡���ϤΥ�åȥϡ��С�������̹��ޥ�ʡˤ϶���̾�Τ���osaka hokkou marina�פDzͶ���ICAO�����ɤ���RJH02�ס��ޤ������Ծ�ϡ�Maishima Keihikoujyou�ס�RJH03�פȤ��Ƥ��ޤ���������Ϥ��줾����������˥塼�����Maishima�ס�osaka�פʤɤ�ʸ���Ǹ����������ǽ�ǡ���ʬ���դ���ICAO�����ɤ�Ʊ����ɽ������ޤ����������� inomaty����γ���������Ϥ�Ʊ�͡��ʤ���ICAO�����ɤǸ������Ƥ�ҥåȤ��ޤ���
�����Ȥ�WED��ǡ��������Τ�ʿ�̿ޤ������Ƥ����ޤ����إ�ѥåɤ����Τʰ��֤����֤������ץ����ͶƳϩ������������դ�ƻϩ�ʤɤҤ�����ͶƳϩ�ġ����Ȥäƺ�ꡢĴ�Ҥ˾�ä����ܤΥ��饦��ɡʥۥå�����ˤޤǺƸ������������������䲫��������ޤ���ޤ��������ʥ٥����������������Ȥ���褦�ˤʤä��Τϼ��ϤǤ��ʥ֥饦����Chrome���ؤ����Ȥ�����������å���˥塼�Υڡ����������ʤ��ʤ�ͥ���ǡ�WED�α�ʸ�ޥ˥奢��餹���ɤळ�Ȥ�����ޤ���!!�ˡ�
������夬�ä��ǡ�����apt.dat�����ǽ��ϡ����Υե����뤬TerraGear�Ǥϥإ�ݡ����������߷ޤ˻Ȥ�졢FlightGear��Ǥ϶����ꥹ�Ȥ�Mapɽ���θ��ǡ����ˤʤ�櫓�Ǥ��͡�
�����ִ��������ʥ�פȶ�¸������ˤϡ�
�����Υإ�ݡ��Ȥ��Ǥˤ���ִ��������ʥ�פξ�ˤɤ��֤��������¤Ϻ��������Ǥ�����
������Ū�ˤϥե�����켰�� inomaty����ˤ����ꤷ�ơ���ǽ�Ǥ�����ִ��������ʥ�פμ����С��������Ȥ߹����ĺ���ޤ��ȹ����ʤΤǤ������ޤ���ư�ƥ��Ȥ������������Τ��Τ����ɤ�ä����ǽ���⤢�ꡢ��Ϥ꼫ʬ�ʤ�ε�ư�Ķ���ɬ�פǤ�����ˡ���褯ʬ����ʤ��ä��Τǡ���������Ȥˤ��ޤ�����
�����إ�ݡ��ȤΤ���������Ω���Ϥ�����Ķ���������ʥ�ˤ��롣
���إ�ݡ��ȼ��դ����μ�����ʥ�ȴ��������ʥ��FlightGear�γ�ĥ�����ʥ�Ȥ���Ʊ����Ͽ�����顢���ޤ��Ťͽߤ�����ɽ������ʤ����ʡ��ʤɤ���Τ������Ȥ�ͤ����ΤǤ����ʾСˡ����⤽����2����1.5���ˤΥ������ǤϾ��������ơ�TerraGear �� tg-construct.exe���Ϸ������ץ������ˤ�����˺�ư���ޤ���Ǥ������ФΥС��Ͻֻ��˿��Ӥޤ�����output�ե�������и����ޤ���ˡ�
�����������ܤ��˹������Ȥ��������ޤ������Ǥ��ޤ�������FlightGear�ǵ�ư����ȡ�����ɽ����ϴ��������ʥ���Ϸ��ǡ����������룱��ʬ�ä����ͳѤ�����˻�ξ����������ʥ������Τ褦���⤫��Ǹ����ޤ������Ĥޤ���Ĥγ�ĥ�����ʥ����Ʊ����Ʊ���������뤳�ȤϽ���ʤ��ΤǤ��͡��ʤ�����������Ū�ʤ��Ȥ����¤Ϥ褯ʬ���äƤ��ޤ���Ǥ����ĺѤߤޤ����
�����إ�ݡ��ȤΤ����Ϸ��������������롣
���Ȥʤ�ȥ�����1����˺�äơ�������Ȥ߹���Ȥ��ϡ����������ʥ�γ�������������Ƥ��������ʤ��褦�Ǥ����ƥ��ȤȤϸ�����inomaty����ˤ����ѿ��줷���ΤǤ������ɤ������ƼϤ��������ޤ��褦�ˡ�(..)��
�������϶�ϥ������ֹ��5168937�פǡ����ͻ��������褤�ΰ������顢�����������λԳ��������ϰ�ΰ����ޤǡ���¸�δ����������ϴޤޤ�ޤ���Τǡ���ˤ�ʤ�Ȥ���줽���Ǥ���
�������ʥ�κ����Ȥʤ뿢���ǡ����ϡ�FlightGear�����륵�������������ط��ǡ��ף���ʬ��ɬ�פǤ������ޥƥꥢ�������ʳ��ǡ�����ʡ����ϡפ� dirt �ˤ����Ȥ������䤿��˰Ť�ť���ˤʤäƤ��ޤ��ޤ������������ˤ��ȼ�ʪ�����뤤�١�����ϤǤ���inomaty�����sand�Ȥ��Ȼפ�����⿿���Ʋ�褷�ޤ������ޥƥꥢ������ƻϩ��Ŵƻ���ʤɤϡ�����������Ѥ�������Ф�����ʤ���ʬ�Ǥ�������Ϥꤢ�����٤����줬ɬ�פǤ��͡�
���������ơ��إ�ݡ��ȤΤ��륷���ʥ������ʰʸ�������ʥ�פȸƤӤޤ��ˤ�̵���������Ǥ��ޤ�������FlightGear����Ͽ����ݤϡ�Additional scenery locations �ε�ư�礬�����դǤ���ɬ�����������ʥ�����������ʥ�������ɬ�פ����ꡢ�դˤ���Ȼ�δĶ��Ǥ�ɽ���۾郎�����ޤ������ޤ��ۤʤ륿����֤ηѤ��ܤϡ����餫�����꤬ʬ���äƤ���С�����2000ft�ʲ��Ǥ��ȸ��Ĥ����礬����ޤ��������ۤ����ۤɤ���Ω���ޤ���Ǥ�����
������ʪ���ä����֤��롧
�������ߥʥ�ӥ���Ǽ�ˣ���Ϻ�������γڤ�AC3D������ޤ�����̵���ӡ������ABN��̵���Τǡ���ŷ�����ܰ��Ȥ��ơ��إ�ݡ������Ϥγ�¦�ˤ���������������ˤϡ�����̹�������סˤ��ꡢ��֤������������Ƥ��ޤ������̤ϻ䤬�ȤäƤ���ABN�ʿ���nm�褫����ǧ��ǽ�ˤ�ꡢ���ʤ�夯���ޤ�����
�����ݤλ����ˤ��ޤ��ȡ����������ȯ���ѥ�����ϡ֣��ôֳ֤ǣ����֤����ꡢ���ô֤��٤ߡפ������Ǥ�����ʪ�ϡ����Ϥ��ŵ壱�Ĥμ��Ϥ˥���β�ž�椬���äơ�����Ⱦʬ���֤��ե�ͥ��������¤ӡ��⤦Ⱦʬ�ˤϲ���ʤ��ĤȤ�����¤�����郎12�ü����Dz�ž����ųݤ��Ǥ���FlightGear��ABN�����椷�Ƥ���xml�ե�������¤���ơ�Ʊ���褦�ʤ��Ȥ������Ȥ��ޤ�������ȯ������ʿ�̤�������䤷��60�ٴֳ֤��¤٤���ΤΡ����ޤ����ֺ����äƸ��äƤ��줺��Ʊ��ȯ���ˤʤäƤ��ޤ���ǰ�Ǥ��������ߤϡ֣��äˣ����֤�ȯ���פDz������Ƥ��ޤ�������ä������ϡ��٤Υ�åȥϡ��С�����������������������ˤθ������ʤ�Ǥ����ĤȤ⤫����������UFO�����֤��ơ֤����Ρפ��������ޤ�����
�����ʤߤˡ�������UFO��ư�桢���֥����������֥ǡ�����d�����ǥ�������̤˥���פ��Ƥ��ޤ�������e������Ȥ��С�OBJECT_SHARED Models/Airport/�פǻϤޤ�ѥ����ƥ����Ȥǽ��Ϥ��졢stg�ե�����˥��ԥڤ��뤳�Ȥ�������Ǥ��͡��Τ�ޤ���Ǥ����IJ��ζ�ϫ�ϰ��Ρ�(^^;)��
�������¤ˤϤʤ��֤�ʿ������Ϥ���ˤϡ�
�������ʥ��ˡ����ޤ��إ�ݡ��Ȥ��и����ޤ����Τǡ����μ¸��˼��ݤ���ޤ�����
���������鵤�ˤʤäƤ���ΤǤ�����FlightGear�Υ����ʥ�Ǥ����Բ�λԳ��Ϥˡ����Ф��и��¤ˤ�¸�ߤ��ʤ����ͤ��и����ޤ����㤨�������ͭ��Į�ն�ˤϡ�ɸ��200ft�Υԥ�ߥåɾ��ξ���������ޤ�������塦���Ĥ�JR�ؼ��դ�����褦�ʤ�ΤǤ������ä�������Υӥ���äƤ⡢����Ǥϲ��س������������Ƥ��ޤ���������ޤ���
��FlightGear�Υ����ʥ�˻Ȥ��Ƥ���ɸ��ǡ����ϡ����ڡ�������ȥ뤫���Ͼ������졼����������SRTM�ˤǤ����顢���餯̩���ϤǤϹ��إӥ�αƶ��ǡ�ʿ�����ɽ��֤˸����Ƥ��ޤ��Τ������Ȼפ��ޤ����Ȥϸ��������������Υ����ʥ2.0�Ǥϡ������ģ�ο������礭��δ�����Ƥ��ޤ����������Ĥδ֤ˤ�ʿ��˲��ɤ���Ƥ��ޤ����Ȥʤ��ɸ�⼫�Τ��Խ�������ˡ������Ϥ��Ǥ��͡��ɤ�����Ƥ����ΤȤ����������դ��ޤ���
�������ǡ����ؼ��ʤȤ������ܤ����Τ������Ǥ���WED�Ƕ������Ϥ��ä������ϡ���ưŪ��ʿ������Ϥ���ޤ����Իԥƥ������㤬�����ˤ��äƤ⡢Urban effect �ε������ĥӥ뷲������ɽ���ͤ��ˤ뤳�Ȥ�ʤ��褦�Ǥ��ʲ�ǯ�������������ĥ��֥������ȤǼ���ޤ��������ӥ뤬�˥祭�˥祭�����ƺ���ޤ����ˡ��ɤ����Ƥ�Ϥˤ������Ȥ�������������̤ϡ������Ȥ��ư����Ф����櫓�Ǥ����Τ�Buncyo�����HP�ˤ⡢�����������ߤ��ɤ����ˤ��ä��Ȼפ��ޤ���
���ǤϤ������Ϥϡ�ɬ�������α�Ĺ�Ǥʤ���Фʤ�ʤ��Τ�������Ȥ�Υ�줿���ˡ�WED�� Boundary �ġ���ʶ������Ϥ��سԤ�������ǽ�ˤǼ��ߤˡ������ϡפ��äƤ⡢�����ȶ������������Τ��Ĥ��ξ��ϤۤȤ�ɼ�ͳ�ˡ��ɤ��Ǥ�ʿ������Ϥ��뤳�Ȥ�����ޤ���
������Ф�����ˡ���ϥإ�ݡ��Ȥ���¦����200���ο�ƻ��ǹ����������̹��ޥ�ʡפ�WED���̾�� Boundary �ġ���������������TerraGear�ǥ����ʥ����ľ���ޤ�������̤�����С������ʥ�˻����̤��ɸ���ʿ�Ϥ��и�������ΤΡ���ǰ�ʤ��龮���ʵ��ͤ��ͤ��Ф���Urban effect�Υӥ�⸽��ޤ�����
�����������Τ褦�ʾ��⡢������˥إ�ѥåɤ�1���äƤ��ޤ��С��������������Ϥ��Ǥ����⤷����Ǥ����饪�֥������Ȥ�褻�Ʊ������������ϥ��ƥ襳��ˡ�����餤�˻��ꤷ�Ƥ��ޤ��С��إ�ѥåɼ��Τ�����ɽ������ʤ��ʤ뤳�Ȥ�ȯ�����ޤ���������ǡ������ʥ���μ�ͳ�٤��礭���ʤꤽ���Ǥ���
���ĤȤ����Ȥ����ǡ����ä��åץ����ɤ�����ĺ���ޤ���³���϶�����ˤ��Ϥ����ޤ���
����2017.10.29�յ���ʸ�桢ʸ������Τ�̾���β�ʸ��ɽ�����ְ�äƤ��ޤ����Τǽ���������ĺ���ޤ��������Ѽ����פ��ޤ���!��
���إ�ݡ��Ȥ����Ǥϼ䤷���Τǡ��������ˤ����åȥϡ��С���¤�äƤ��ޤ��ޤ����������ˤϡ���90��������Ω�ɤʥ���åס�����Φ�Ȥ����뷹��ϩ�ˤ����äơ��������ۤ�ˤ䤫�ˤ���С���嵡����������ȯ�ʡ����Ƥˤ�äƤ����Ǥ��������dz��Ѥϥ�åȥϡ��С��ΤޤޡʲͶ��δ�������Ǽ�ˤϺ�餺�ˡ��Ͼ�ǵ��Τ�ư��ǽ�ˤ��ơ���嵡���Ϥ˻Ȥ���褦�ˤ��ޤ�����
���ޤ����إ�ݡ�����¦���Ӥζ���̿��Ƥ����顢�Ͼ��������������ϩ�Ȥ����פ��ʤ��������Ƥ�ȯ�����ޤ������¤Ϥ��������Ω���Ϥϡ�2008ǯ���ؤ�Ͷ�פ��ᥤ����ˤ���Ϥ����ä����Ǥ������δط��ǡ������Ծ�פ����ߤ��줿��ΤΡ����س��Ť��̵��˼��줿�塢���٤Ⳬ�����ʤ��ޤ�������ĤĤ���褦�Ǥ������ߡ������ϩ����ü�ն�ϥ����ȥ���������ü�ϥ��饦��ɡ���¦�ϥ����ȥ�����ʤɤˤʤäƤ��ޤ�����ä����ʤ��Τdz���ϩ��ͶƳϩ��Ƹ����ơ�������٤�褦�ˤ��ޤ�����
���Ȥ�������ǡĵ����դ��С��鷺��������ľ����ˡ����Ĥμ������Ծ졦�إ�ݡ��Ȥ��¤֤��Ȥˤʤ�ޤ�����
�����ޤ����إ�ݡ��Ȥ�¤�롧
����������˥إ�ݡ��Ȥ�������Τϡ�������ꤺ�äȾ���������ץ�ʤΤǡ���ˤ����������Ȼפä�����Ǥ���
��3ǯ�����إꥳ�ץ�����Ǯ�椷�ơ��ٻλ�ĺ�ؤΥ�ɡ����ߤ�夲�Ƹ��ե饤�Ȥʤɤ�ֳƼ�����ˤĤ��ơץե�������Ϣ�ܡּ�õ���ˡ��ι�����סʤ��Σ��ˤǤ��Ҳ𤷤��������֥إꥳ�ץ�����Ĥ�ABC�סʥ�������MOOK��2000�ߡˤȤ����ܤ��ɤߡ������إ�ݡ��Ȥ�¸�ߤ��Τ�ޤ��������ͣ��θ����إ�ݡ��Ȥǡ�ǯ����Φ���������إ�ݡ��Ȥ˼�������2�̤��Ȥ��������ʥ����ߥʥ�ӥ�˵ձ߿����δ��������������ǥ��������ơ����Һ�äƤߤ����ʤ�ޤ�����
���ޤ���������Ǥ������إ�ѥåɤΰ��֤䥵���������̡�ɸ��ʤɤϥͥåȤǤ���Ƚ�����ޤ������������Τβ�����ɬ�פǤ������������ʤ�ܤ���ʿ�̿ޤ���ɽ����Ƥ��ޤ����ۤ��˸��Ϥμ̿��줳�������GoogleEarth��������ơ����̥����å����ʪ�κ����˻Ȥ��ޤ�����������GoogleEarth�ο����ο��������դǡ����ä����߸Ϥ�β��������ޤ��ȡ������ʤʹӤ��ϤˤʤäƤ��ޤ��ޤ��������Ͽ��Ф䡢����ε���ͤˤ�������ΤǤ��͡�
������WED��ư���ơ������ˡ�Maishima�פȤ����ե�������äƵ�ư����˥塼�С������Create Airport�פ����ơ�̾�Τ��[H]Maishima Heliport�פȤ��ޤ��������¤��إ�ݡ��Ȥ�ICAO�����ɤ��դ��Ƥ��ʤ��ΤǤ�����������ص����RJH01�פȤ��ޤ�������Ǥ��ä������嵡���ϤΥ�åȥϡ��С�������̹��ޥ�ʡˤ϶���̾�Τ���osaka hokkou marina�פDzͶ���ICAO�����ɤ���RJH02�ס��ޤ������Ծ�ϡ�Maishima Keihikoujyou�ס�RJH03�פȤ��Ƥ��ޤ���������Ϥ��줾����������˥塼�����Maishima�ס�osaka�פʤɤ�ʸ���Ǹ����������ǽ�ǡ���ʬ���դ���ICAO�����ɤ�Ʊ����ɽ������ޤ����������� inomaty����γ���������Ϥ�Ʊ�͡��ʤ���ICAO�����ɤǸ������Ƥ�ҥåȤ��ޤ���
�����Ȥ�WED��ǡ��������Τ�ʿ�̿ޤ������Ƥ����ޤ����إ�ѥåɤ����Τʰ��֤����֤������ץ����ͶƳϩ������������դ�ƻϩ�ʤɤҤ�����ͶƳϩ�ġ����Ȥäƺ�ꡢĴ�Ҥ˾�ä����ܤΥ��饦��ɡʥۥå�����ˤޤǺƸ������������������䲫��������ޤ���ޤ��������ʥ٥����������������Ȥ���褦�ˤʤä��Τϼ��ϤǤ��ʥ֥饦����Chrome���ؤ����Ȥ�����������å���˥塼�Υڡ����������ʤ��ʤ�ͥ���ǡ�WED�α�ʸ�ޥ˥奢��餹���ɤळ�Ȥ�����ޤ���!!�ˡ�
������夬�ä��ǡ�����apt.dat�����ǽ��ϡ����Υե����뤬TerraGear�Ǥϥإ�ݡ����������߷ޤ˻Ȥ�졢FlightGear��Ǥ϶����ꥹ�Ȥ�Mapɽ���θ��ǡ����ˤʤ�櫓�Ǥ��͡�
�����ִ��������ʥ�פȶ�¸������ˤϡ�
�����Υإ�ݡ��Ȥ��Ǥˤ���ִ��������ʥ�פξ�ˤɤ��֤��������¤Ϻ��������Ǥ�����
������Ū�ˤϥե�����켰�� inomaty����ˤ����ꤷ�ơ���ǽ�Ǥ�����ִ��������ʥ�פμ����С��������Ȥ߹����ĺ���ޤ��ȹ����ʤΤǤ������ޤ���ư�ƥ��Ȥ������������Τ��Τ����ɤ�ä����ǽ���⤢�ꡢ��Ϥ꼫ʬ�ʤ�ε�ư�Ķ���ɬ�פǤ�����ˡ���褯ʬ����ʤ��ä��Τǡ���������Ȥˤ��ޤ�����
�����إ�ݡ��ȤΤ���������Ω���Ϥ�����Ķ���������ʥ�ˤ��롣
���إ�ݡ��ȼ��դ����μ�����ʥ�ȴ��������ʥ��FlightGear�γ�ĥ�����ʥ�Ȥ���Ʊ����Ͽ�����顢���ޤ��Ťͽߤ�����ɽ������ʤ����ʡ��ʤɤ���Τ������Ȥ�ͤ����ΤǤ����ʾСˡ����⤽����2����1.5���ˤΥ������ǤϾ��������ơ�TerraGear �� tg-construct.exe���Ϸ������ץ������ˤ�����˺�ư���ޤ���Ǥ������ФΥС��Ͻֻ��˿��Ӥޤ�����output�ե�������и����ޤ���ˡ�
�����������ܤ��˹������Ȥ��������ޤ������Ǥ��ޤ�������FlightGear�ǵ�ư����ȡ�����ɽ����ϴ��������ʥ���Ϸ��ǡ����������룱��ʬ�ä����ͳѤ�����˻�ξ����������ʥ������Τ褦���⤫��Ǹ����ޤ������Ĥޤ���Ĥγ�ĥ�����ʥ����Ʊ����Ʊ���������뤳�ȤϽ���ʤ��ΤǤ��͡��ʤ�����������Ū�ʤ��Ȥ����¤Ϥ褯ʬ���äƤ��ޤ���Ǥ����ĺѤߤޤ����
�����إ�ݡ��ȤΤ����Ϸ��������������롣
���Ȥʤ�ȥ�����1����˺�äơ�������Ȥ߹���Ȥ��ϡ����������ʥ�γ�������������Ƥ��������ʤ��褦�Ǥ����ƥ��ȤȤϸ�����inomaty����ˤ����ѿ��줷���ΤǤ������ɤ������ƼϤ��������ޤ��褦�ˡ�(..)��
�������϶�ϥ������ֹ��5168937�פǡ����ͻ��������褤�ΰ������顢�����������λԳ��������ϰ�ΰ����ޤǡ���¸�δ����������ϴޤޤ�ޤ���Τǡ���ˤ�ʤ�Ȥ���줽���Ǥ���
�������ʥ�κ����Ȥʤ뿢���ǡ����ϡ�FlightGear�����륵�������������ط��ǡ��ף���ʬ��ɬ�פǤ������ޥƥꥢ�������ʳ��ǡ�����ʡ����ϡפ� dirt �ˤ����Ȥ������䤿��˰Ť�ť���ˤʤäƤ��ޤ��ޤ������������ˤ��ȼ�ʪ�����뤤�١�����ϤǤ���inomaty�����sand�Ȥ��Ȼפ�����⿿���Ʋ�褷�ޤ������ޥƥꥢ������ƻϩ��Ŵƻ���ʤɤϡ�����������Ѥ�������Ф�����ʤ���ʬ�Ǥ�������Ϥꤢ�����٤����줬ɬ�פǤ��͡�
���������ơ��إ�ݡ��ȤΤ��륷���ʥ������ʰʸ�������ʥ�פȸƤӤޤ��ˤ�̵���������Ǥ��ޤ�������FlightGear����Ͽ����ݤϡ�Additional scenery locations �ε�ư�礬�����դǤ���ɬ�����������ʥ�����������ʥ�������ɬ�פ����ꡢ�դˤ���Ȼ�δĶ��Ǥ�ɽ���۾郎�����ޤ������ޤ��ۤʤ륿����֤ηѤ��ܤϡ����餫�����꤬ʬ���äƤ���С�����2000ft�ʲ��Ǥ��ȸ��Ĥ����礬����ޤ��������ۤ����ۤɤ���Ω���ޤ���Ǥ�����
������ʪ���ä����֤��롧
�������ߥʥ�ӥ���Ǽ�ˣ���Ϻ�������γڤ�AC3D������ޤ�����̵���ӡ������ABN��̵���Τǡ���ŷ�����ܰ��Ȥ��ơ��إ�ݡ������Ϥγ�¦�ˤ���������������ˤϡ�����̹�������סˤ��ꡢ��֤������������Ƥ��ޤ������̤ϻ䤬�ȤäƤ���ABN�ʿ���nm�褫����ǧ��ǽ�ˤ�ꡢ���ʤ�夯���ޤ�����
�����ݤλ����ˤ��ޤ��ȡ����������ȯ���ѥ�����ϡ֣��ôֳ֤ǣ����֤����ꡢ���ô֤��٤ߡפ������Ǥ�����ʪ�ϡ����Ϥ��ŵ壱�Ĥμ��Ϥ˥���β�ž�椬���äơ�����Ⱦʬ���֤��ե�ͥ��������¤ӡ��⤦Ⱦʬ�ˤϲ���ʤ��ĤȤ�����¤�����郎12�ü����Dz�ž����ųݤ��Ǥ���FlightGear��ABN�����椷�Ƥ���xml�ե�������¤���ơ�Ʊ���褦�ʤ��Ȥ������Ȥ��ޤ�������ȯ������ʿ�̤�������䤷��60�ٴֳ֤��¤٤���ΤΡ����ޤ����ֺ����äƸ��äƤ��줺��Ʊ��ȯ���ˤʤäƤ��ޤ���ǰ�Ǥ��������ߤϡ֣��äˣ����֤�ȯ���פDz������Ƥ��ޤ�������ä������ϡ��٤Υ�åȥϡ��С�����������������������ˤθ������ʤ�Ǥ����ĤȤ⤫����������UFO�����֤��ơ֤����Ρפ��������ޤ�����
�����ʤߤˡ�������UFO��ư�桢���֥����������֥ǡ�����d�����ǥ�������̤˥���פ��Ƥ��ޤ�������e������Ȥ��С�OBJECT_SHARED Models/Airport/�פǻϤޤ�ѥ����ƥ����Ȥǽ��Ϥ��졢stg�ե�����˥��ԥڤ��뤳�Ȥ�������Ǥ��͡��Τ�ޤ���Ǥ����IJ��ζ�ϫ�ϰ��Ρ�(^^;)��
�������¤ˤϤʤ��֤�ʿ������Ϥ���ˤϡ�
�������ʥ��ˡ����ޤ��إ�ݡ��Ȥ��и����ޤ����Τǡ����μ¸��˼��ݤ���ޤ�����
���������鵤�ˤʤäƤ���ΤǤ�����FlightGear�Υ����ʥ�Ǥ����Բ�λԳ��Ϥˡ����Ф��и��¤ˤ�¸�ߤ��ʤ����ͤ��и����ޤ����㤨�������ͭ��Į�ն�ˤϡ�ɸ��200ft�Υԥ�ߥåɾ��ξ���������ޤ�������塦���Ĥ�JR�ؼ��դ�����褦�ʤ�ΤǤ������ä�������Υӥ���äƤ⡢����Ǥϲ��س������������Ƥ��ޤ���������ޤ���
��FlightGear�Υ����ʥ�˻Ȥ��Ƥ���ɸ��ǡ����ϡ����ڡ�������ȥ뤫���Ͼ������졼����������SRTM�ˤǤ����顢���餯̩���ϤǤϹ��إӥ�αƶ��ǡ�ʿ�����ɽ��֤˸����Ƥ��ޤ��Τ������Ȼפ��ޤ����Ȥϸ��������������Υ����ʥ2.0�Ǥϡ������ģ�ο������礭��δ�����Ƥ��ޤ����������Ĥδ֤ˤ�ʿ��˲��ɤ���Ƥ��ޤ����Ȥʤ��ɸ�⼫�Τ��Խ�������ˡ������Ϥ��Ǥ��͡��ɤ�����Ƥ����ΤȤ����������դ��ޤ���
�������ǡ����ؼ��ʤȤ������ܤ����Τ������Ǥ���WED�Ƕ������Ϥ��ä������ϡ���ưŪ��ʿ������Ϥ���ޤ����Իԥƥ������㤬�����ˤ��äƤ⡢Urban effect �ε������ĥӥ뷲������ɽ���ͤ��ˤ뤳�Ȥ�ʤ��褦�Ǥ��ʲ�ǯ�������������ĥ��֥������ȤǼ���ޤ��������ӥ뤬�˥祭�˥祭�����ƺ���ޤ����ˡ��ɤ����Ƥ�Ϥˤ������Ȥ�������������̤ϡ������Ȥ��ư����Ф����櫓�Ǥ����Τ�Buncyo�����HP�ˤ⡢�����������ߤ��ɤ����ˤ��ä��Ȼפ��ޤ���
���ǤϤ������Ϥϡ�ɬ�������α�Ĺ�Ǥʤ���Фʤ�ʤ��Τ�������Ȥ�Υ�줿���ˡ�WED�� Boundary �ġ���ʶ������Ϥ��سԤ�������ǽ�ˤǼ��ߤˡ������ϡפ��äƤ⡢�����ȶ������������Τ��Ĥ��ξ��ϤۤȤ�ɼ�ͳ�ˡ��ɤ��Ǥ�ʿ������Ϥ��뤳�Ȥ�����ޤ���
������Ф�����ˡ���ϥإ�ݡ��Ȥ���¦����200���ο�ƻ��ǹ����������̹��ޥ�ʡפ�WED���̾�� Boundary �ġ���������������TerraGear�ǥ����ʥ����ľ���ޤ�������̤�����С������ʥ�˻����̤��ɸ���ʿ�Ϥ��и�������ΤΡ���ǰ�ʤ��龮���ʵ��ͤ��ͤ��Ф���Urban effect�Υӥ�⸽��ޤ�����
�����������Τ褦�ʾ��⡢������˥إ�ѥåɤ�1���äƤ��ޤ��С��������������Ϥ��Ǥ����⤷����Ǥ����饪�֥������Ȥ�褻�Ʊ������������ϥ��ƥ襳��ˡ�����餤�˻��ꤷ�Ƥ��ޤ��С��إ�ѥåɼ��Τ�����ɽ������ʤ��ʤ뤳�Ȥ�ȯ�����ޤ���������ǡ������ʥ���μ�ͳ�٤��礭���ʤꤽ���Ǥ���
���ĤȤ����Ȥ����ǡ����ä��åץ����ɤ�����ĺ���ޤ���³���϶�����ˤ��Ϥ����ޤ���
����2017.10.29�յ���ʸ�桢ʸ������Τ�̾���β�ʸ��ɽ�����ְ�äƤ��ޤ����Τǽ���������ĺ���ޤ��������Ѽ����פ��ޤ���!��
��ɼ��:18
ʿ����:4.44
inomaty
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
����Ф�ϡ�hide����inomaty�Ǥ���
�إ�ݡ��Ȥϸ����äƤ����Τǡ��������Ƥ����������꤬�����Ǥ�(*^^*)
�Ŀ�Ū�˵��ˤʤ�Τϥ���åפǤ��礦����������ˤ⤢��褦�Ǥ����ɡ��ɤ���äƺ������Ǻ�����˸��ߤϻȤ��Ƥ��ʤ��褦�Ǥ�����̵���ä����Ȥˤ��Ȥ����Ȥ����ΤǤ���äȳڤ��ߤǤ���
��ð�����Ϻ��������ˤʤä������ʤޤʤ�(������)�Τǡ�����ʳ��η�ʪ��ޤä����ʤ�Ǥ���ޤ��Ŀͤˤϻ��Υ����٥�����������ΤϤ�Ϥ����褦�Ǥ�����Ĺ�ˤ��Ԥ�������(^_^;)��
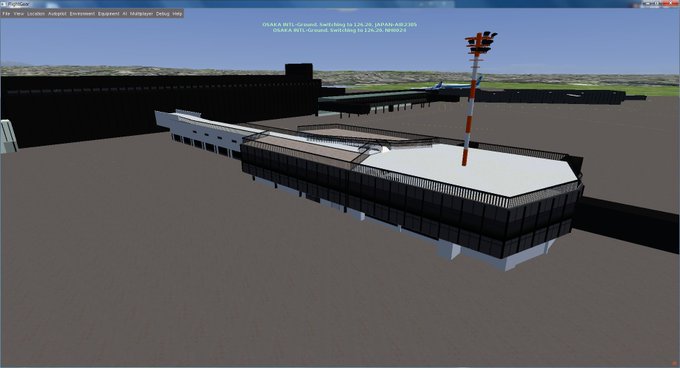
���ѡ�Ƭ��[H]���ä������ɤ����Ȼפ��ޤ����Ȥ����Τ⾮������Ϥ��ä��ݤ�x-plane scenery gateway�ˤ�夲�Ƥߤޤ�������[H]�λ��Ϥ⤦�ȤäƤʤ��Ǥ����ͤäѤͤ�졢WED��̾���ν��������٤Ǥ��Ѥ���줺������Ⱦʬ����Ƥ��ޤ���scenery gateway��aptdat��夲��Ĥ��Ǥ����顢����̾���ѹ������ᤷ�ޤ����Ĥ��Ǥ�ICAO���쥿����̵�������Σ��쥿��������Ƭ��X���դ��뤽���Ǥ�(���ij�����XRJSV����Ͽ���Ƥ���ޤ�)��
�Ϸ��Υ�����ǡ����η�Ǥ������ɤ����ٳݤ��뤫ʬ����ޤ�����Ū�ˤ϶����ǡ������Ϸ��ǡ������̸ĥǡ����ˤ��ơ����ޤ��Ҥ���褦�ˤ���(Draping�Ȥ����餷���Ǥ��Ѹ�Wiki TerraGear_support_for_Draping)������ˤ�äƶ������Ϸ��˼��뤿�Ӥ�TerraGear��Ĺ�������ԤĤȤ������Ȥ�̵���ʤ�ΤǤϤʤ����Ȼפ��ޤ������ºݤɤ��ʤ뤫ʬ����ʤ��ΤǤʤ�Ȥ�����ޤ����ߤޤ������Ȥ��Ƥ�hide����Τ�ä��̤������ޤ������������Τ�����������Ȼפ��ޤ��������ޤΡ����ϡ���ʬ������潧�λ��꤬¿���褦�˻פ����Τǡ���sand�פ����ޤ����������դⶨ�Ĥ������줷��ɽ��ä������ɤ����⤷��ޤ���͡�;�̤Ǥ�������εܾ륨�ꥢ�ƥ��ȥե�����⻳��������ʡ��������������������ξ�ˤ�����֤ˤʤäƤޤ�(�����ϡ�)��
����˴ؤ��ƤǤ����ۺ����������RW09����ˤ������������Ω���ޤ��͡�5������ä�Ƭ��12RPM�Dz�뤳�Ȥ�1�ä˰��������꤬�����Ȥ�����¤�ˤʤäƤޤ�����¦����������Ȥ��Τ��������ޤ�������ʬ�κ����Ƿ빽Ǻ�ߡ��桹ʣ���ʻ��Ȥߤξ�ˤ��������˥ե����뤬����Ǥ������Ȼפ��ޤ��Τǰ�̣�������⤷��ޤ���(�¤�ALS�б������Ū�ʤ��)���ե����뤬�夬�äƤ����餳����Ǥ���ʤ����ͤ��Ƥߤޤ���
�Ϸ��Τ���������ʬ��ľ���ˤ�(���Ȥä�����̵���Ǥ�����)ľ��BTG�ե������Blender(2.4.x�ϤΤ�)���ɤ�륹����ץȤ�������ޤ�(�Ѹ�Wiki Blender_and_BTG)��SRTM���Խ����ƽ��Ϥ�����ˡ���Τ�ʤ��Τǻ�Ϥ��줷����ˡ���Τ�ޤ���4m�������ڤ��줿������Ϥ���Ȥ��ˤǤ�Ȥ������ȻפäƤ��ޤ������ɤ����褦���ʡ��ȹͤ��Ƥ��ޤ���������ˤ���ʿ��ˤ��뤿��˥إ�ѥåɺ��Ȥ��������ǥ��������Ȼפ��ޤ���
�Ȥ���������Ĺ���ʤ��äƤ��ޤ��ޤ����������åץ����ɤ����Τ�ڤ��ߤˤ��Ƥ���ޤ�
�إ�ݡ��Ȥϸ����äƤ����Τǡ��������Ƥ����������꤬�����Ǥ�(*^^*)
�Ŀ�Ū�˵��ˤʤ�Τϥ���åפǤ��礦����������ˤ⤢��褦�Ǥ����ɡ��ɤ���äƺ������Ǻ�����˸��ߤϻȤ��Ƥ��ʤ��褦�Ǥ�����̵���ä����Ȥˤ��Ȥ����Ȥ����ΤǤ���äȳڤ��ߤǤ���
��ð�����Ϻ��������ˤʤä������ʤޤʤ�(������)�Τǡ�����ʳ��η�ʪ��ޤä����ʤ�Ǥ���ޤ��Ŀͤˤϻ��Υ����٥�����������ΤϤ�Ϥ����褦�Ǥ�����Ĺ�ˤ��Ԥ�������(^_^;)��
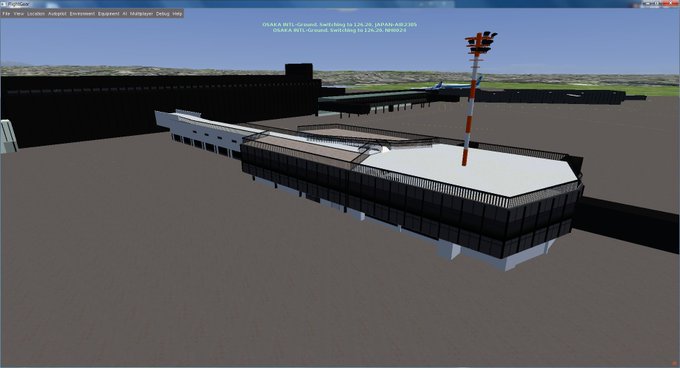
���ѡ�
̾�Τ��[H]Maishima Heliport�פȤ��ޤ�����
�Ϸ��Υ�����ǡ����η�Ǥ������ɤ����ٳݤ��뤫ʬ����ޤ�����Ū�ˤ϶����ǡ������Ϸ��ǡ������̸ĥǡ����ˤ��ơ����ޤ��Ҥ���褦�ˤ���(Draping�Ȥ����餷���Ǥ��Ѹ�Wiki TerraGear_support_for_Draping)������ˤ�äƶ������Ϸ��˼��뤿�Ӥ�TerraGear��Ĺ�������ԤĤȤ������Ȥ�̵���ʤ�ΤǤϤʤ����Ȼפ��ޤ������ºݤɤ��ʤ뤫ʬ����ʤ��ΤǤʤ�Ȥ�����ޤ����ߤޤ������Ȥ��Ƥ�hide����Τ�ä��̤������ޤ������������Τ�����������Ȼפ��ޤ��������ޤΡ����ϡ���ʬ������潧�λ��꤬¿���褦�˻פ����Τǡ���sand�פ����ޤ����������դⶨ�Ĥ������줷��ɽ��ä������ɤ����⤷��ޤ���͡�;�̤Ǥ�������εܾ륨�ꥢ�ƥ��ȥե�����⻳��������ʡ��������������������ξ�ˤ�����֤ˤʤäƤޤ�(�����ϡ�)��
����˴ؤ��ƤǤ����ۺ����������RW09����ˤ������������Ω���ޤ��͡�5������ä�Ƭ��12RPM�Dz�뤳�Ȥ�1�ä˰��������꤬�����Ȥ�����¤�ˤʤäƤޤ�����¦����������Ȥ��Τ��������ޤ�������ʬ�κ����Ƿ빽Ǻ�ߡ��桹ʣ���ʻ��Ȥߤξ�ˤ��������˥ե����뤬����Ǥ������Ȼפ��ޤ��Τǰ�̣�������⤷��ޤ���(�¤�ALS�б������Ū�ʤ��)���ե����뤬�夬�äƤ����餳����Ǥ���ʤ����ͤ��Ƥߤޤ���
�Ϸ��Τ���������ʬ��ľ���ˤ�(���Ȥä�����̵���Ǥ�����)ľ��BTG�ե������Blender(2.4.x�ϤΤ�)���ɤ�륹����ץȤ�������ޤ�(�Ѹ�Wiki Blender_and_BTG)��SRTM���Խ����ƽ��Ϥ�����ˡ���Τ�ʤ��Τǻ�Ϥ��줷����ˡ���Τ�ޤ���4m�������ڤ��줿������Ϥ���Ȥ��ˤǤ�Ȥ������ȻפäƤ��ޤ������ɤ����褦���ʡ��ȹͤ��Ƥ��ޤ���������ˤ���ʿ��ˤ��뤿��˥إ�ѥåɺ��Ȥ��������ǥ��������Ȼפ��ޤ���

�Ȥ���������Ĺ���ʤ��äƤ��ޤ��ޤ����������åץ����ɤ����Τ�ڤ��ߤˤ��Ƥ���ޤ�

--
OS:Win7 Pro 64bit
�� Ubuntu14.04LTS
FG version:Win7:3.4,2017.3.1
���������� Ubuntu:2016.1.1,2016.2.0
��ɼ��:19
ʿ����:6.32
hide
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
hide�Ǥ���inomaty����ˤ��ϡ�
�������ҥ�Ȥ�ĺ���ޤ��ơ����꤬�Ȥ��������ޤ������إ�ݡ��Ȥ���¾�ϡ����줫��⤦���������ߤޤ��ơ��ܴۤ������ʳ��ˤʤäƤ��ޤ���������ܤ˳ݤ��褦�ȻפäƤ���ޤ��������������˽Ф������ѻ������äƤ��ޤ����㴳�μ�ľ����Ȥ䤴�Ҳ�ʸ����֤���������ؤ������Ǥ��ޤ������Ƕ��̤Ǥ�(^^)��
����ð�����ϡ��������Ƥ����ޤ��������������ˤ����֤��ʤ�ΤǤ��͡�����ǯ���˺�ꤿ���Ȼפ�����ʪ�����Ф餯�夬�ä���ߤꤿ�ꤷ���ΤǤ����������Τ褦�ʹ�¤�����������ˤ���塢��ʪ��������̯�������Ϥ��ޤäƤ��ơ��פä���ꤺ�ä�ʣ���������ɤ��ǥե���ᤷ�Ƥ���餷�������뤫���ޤȤ��ʤ��Ȼפä���ǰ���ޤ�����
����������η濫�꤬�Ȥ��������ޤ�������Ω���ʤ������Τ�ޤ���Ĵ�٤Ƥߤޤ���
�������ҥ�Ȥ�ĺ���ޤ��ơ����꤬�Ȥ��������ޤ������إ�ݡ��Ȥ���¾�ϡ����줫��⤦���������ߤޤ��ơ��ܴۤ������ʳ��ˤʤäƤ��ޤ���������ܤ˳ݤ��褦�ȻפäƤ���ޤ��������������˽Ф������ѻ������äƤ��ޤ����㴳�μ�ľ����Ȥ䤴�Ҳ�ʸ����֤���������ؤ������Ǥ��ޤ������Ƕ��̤Ǥ�(^^)��
����ð�����ϡ��������Ƥ����ޤ��������������ˤ����֤��ʤ�ΤǤ��͡�����ǯ���˺�ꤿ���Ȼפ�����ʪ�����Ф餯�夬�ä���ߤꤿ�ꤷ���ΤǤ����������Τ褦�ʹ�¤�����������ˤ���塢��ʪ��������̯�������Ϥ��ޤäƤ��ơ��פä���ꤺ�ä�ʣ���������ɤ��ǥե���ᤷ�Ƥ���餷�������뤫���ޤȤ��ʤ��Ȼפä���ǰ���ޤ�����
����������η濫�꤬�Ȥ��������ޤ�������Ω���ʤ������Τ�ޤ���Ĵ�٤Ƥߤޤ���
��ɼ��:23
ʿ����:4.35
hide
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
hide�Ǥ����������ʤޤ����ޡ˥إ�ݡ��������³�����Ϥ����ޤ���Ĺʸ�Ǥ����ʤ���!!
������ϥإ�ݡ��ȼ��դ�����ߡ���¦���дߤˤ����åȥϡ��С�������̹��ޥ�ʡפ䡢���Ĥƥإ�ݡ��Ȥ�����¤��줿�������Ծ�פ�Ƹ����뤪�äǤ������������ʥ�� Maishima-fg-CustomScenery �Ȥ��ơ�JP���؎��ގŎَ��ގ��ݎێ��Ďޤ˥��åפ�����ĺ���ޤ������ʤ�����ĺ������ϡ�ʸ����������ɬ��������������
�����Ҹ˷��䶶���롧
�����������إ�ݡ��Ȥ�����������ΤΡ����θ���ӥ�R44��EC135P2��ȯ��ƥ��Ȥ�Ťͤ��Ȥ������ɤ���̿��Ǹ����·ʤ�ʷ�ϵ����㤦�����Ȥ������ݤ�����ޤ�����
����90ǯ�塢����ϸ��Τ������˽��褿���Ω���Ϥǡ�����Ͷ�פ�ƨ���ưʹߡ������Τ�����Ǥ���ä���ʤ��¤ꡢ����ޤ�����λȤ�ƻ��̵�������Ǥ������ߤ�����ʬ���Ƽ殺�饦��ɤ���ࡢ���Ϥ�ʤ���Ƥ��ޤ�������¦�Υإ�ݡ����ն�������㳰�ǡ�����ͤ��������å������ʲ����ť������ˤ䡢�����ʪή�����������ޤäƤ��ޤ������äƥإ�Υ��ץ�������볦�ˤϡ�����ʤ�����¤�����櫓�ǡ�¿���Ϸ�ʪ��Ƹ����ʤ��ȡ��ºݤȤ���Υ�줿���Ծ��ˤʤäƤ��ޤ��ޤ���
���Ĥ����ǥ���ץ�ʤ��顢���狼�ӥ����ޤ�������Ϥ�ϡ��䤿�����Ω�ı�ť�����졣�ּ�������ľ���Ϥʤ����פ������ʤޤ�ǥ���ȥ˥��������ǥ��ˤȤ������������ȥꥢ�η��۲Ȥκ�ǡ��̿��Ǹ���¤�ϡ����ɼ�ʥơ��ޥѡ����Ȥ����פ��ޤ����Ѥ���1�ܤޤǡ������ϥȥ���ޤǶŤäƤ��뤽���ǡ�������Ƕ�Τ����ޤꡣ������Ȥ��꤬�ʤ��Τ�ñ���Ȣ���ˤ��ơ��⤵120���Ȥ������ͤζ��å����Υ����ʬ�����ϡ�������������ȤäƤ���餷�����餻�ޤ�����
�����Υӥ��ǡ�������֤����Ȥ������֤���㡢���ä����Ť��ʤ��ʤ��פȼ´������Ծ����Ѳ���ȩ�Ǵ������ޤ������ޤ��������Ǥ��������Ƕ��٤�ʪή�Ҹˤ⣳��ۤ������������ϴ�ά�������ȥ�å�����겼�ꤹ����פ���ñ��ʱ����ǺƸ����ơ����Ϥμ̿���į��ʤ���ƥ�������������ޤ�����
�������η�ʪ���¤٤�ȡ��ޤ��ޤ����Ω���Ϥ餷���ʤäƤ��ޤ�����Ʊ���ʹԤǥ�åȥϡ��С����äƤ����Τǡ��ϡ��С��ȥ���å��������ּ�ĥ���־���綶�פ��ߤ����ʤ�ޤ�������ʹ⤵��90���ˤϰ��ܤʤΤ����Ū���䤹�����Ǥ��������夬��̯�˾岼��ȿ�äơ����ޤ��˥����֤��Ƥ��ޤ�������ʤ�Τϡ��ɤ���������Ф����ΤǤ��礦���ġ�
���ͥåȤ�õ����ä��鹬���ˤ⡢������λ��̿ޤ����Ĥ���ޤ�������������ˣ������ζ�������Ե���ƹ�Τ�����¤��Τ�Ʊ���ֲ����Ф��פε�ˡ����������гھ��ĤȻפä��ΤǤ������̾��̤�1�ѡ�1�ԥ�����Dz������ä��Ȥ������礭������AC3D���ɤ�Ǥ���ޤ���10ʬ��1�˽̾����ƺ�Ȥ˳ݤ���ޤ�����
�������������ξ¦�ز����Ф���ʤᡢ��ƻ�ϥ����ե���ȳ���ϩ�Υƥ��������Ž�äơ���ƻ��ʬ��·ʤ�Ʊ���Ф��忧�����ȤϺ����褯������ȶ���δ֤Υ磻���ĥ�äƤ����д����Ǥ�����Ȥ���UFO�Ǹ�������֤����Ȥ������������ĥ�������10ʬ��1�ΤޤޤǤ���(^^;)��
��3��������1000��γ����ݤ��ƺ����֡��֤ʤ��UFO���Ϥ�����Ȥ������ʤ�ˤĤ�������Υ磻�䷲���·��̤ꡢƬ��ؤ��ꤸ������;��˹����äƸ������ʤ��ʤ����㤷�ޤ�����
�����ޥ�ʤμ���ϥ����졼�إ�ѥåɡ��������ϩ����
�������ϥإ�ݡ��Ȥ��дߤˤ��롢����̹��ʤۤä����˥ޥ�ʤ��������ޤ�������⾯������ޤ�������ɸ��ǡ����˸����Τ���ӥ볹��ʿ������Ϥ���ƥ��Ȥȡ��緿�Υ���åפ���Ѥ��ƿ�嵡���Ϥˤ��Ƥߤ褦���Ȥ����Τ���Ū�Ǥ�����ϰ��������Ͷ���������˥���åפ��Ǽ�ˤ��ߤ��������Ѥο�嵡���Ϥˤ�����ɤ����ȶ��ۤ��Ƥ��ޤ����������������ȶ����˲Ͷ��λ��ߤ��դ������ϡ��ºߤΥ�åȥϡ��С������Ѥ��ƿ�嵡���Ѥ�����������ʤ褦�˻פ��ޤ����ʤ�к��إ�ݡ��Ȥȥ��åȤǺ�äƤ��ޤ������Ȥ����櫓�Ǥ���
���ǽ�ϥإ�ݡ��Ȥ�WED�ǡ����ˡ������ϡפȤ��ơ�Boundary�⡼�ɤǥޥ�����Ϥ����������ΤǤ������ƥ����ѥ����ʥ��ư���Ƥߤ�ȡ��ʤ����إ�ݡ��Ȥ����Ϥ������Ф����������������������ߥʥ�ӥ���Ǽ�ˤ�����⤤�Ƥ��ޤ��ޤ�����������������ɸ��˱ƶ����Ф�褦�Ǥ��������ǥޥ�ʤϥץ������塢��Ω���������Ȥ��ƺ��ľ�����Ȥˤ��ޤ��������������פ�Seaport�Ǥ���
�����ۤ�ICAO�����ɡ�RJH02�פ�Ϳ���ơʸ������Ǥϡ��ޤ���X�פ��դ��Ƥ��ޤ��ˡ����̤����ݥå������û�������졼��ʳ����ӡˤ����ꡣ�����ǵ��Τ�ư�����Ƴ����ޤǥ���������Υ�������Ԥ��Ĥ��Ǥ����Ȥ����������졼������ꤹ��ȡ��ʤ�����ɽ�Υƥ������㤬�ӥ�ӥ꿶ư����ʤɡ�ɽ���ȥ�֥뤬³���ޤ������ºݤα��ѻ��ϡ���Ͽ�嵡���Ͼ�ǵ�ư���ƥ���åפ��鳤�˹ߤ����������⤹��Φ�Ȥ�����Ĥ��ʼ��������������Ʊ���ˤǤ��Τǡ������Ͽ��ǵ�ư���뵡ǽ�����פǤ��������ǥ����졼����ơ����ץ������������������˥إ�ѥåɤ��ߤ����Ȥ���������˲���ɽ�������褦�ˤʤ�ޤ����ʳ���ϩ�������졼�إ�ѥåɤ�����Ĥ��ߤ��ʤ��ȡ�WED�����顼��Ф��ޤ��ˡ�
�����Τ��ȡ������졼��ȥإ�ݡ��Ȥ�ʻ�Ѥ��ޤ����������������פˤ�äơ������줫����������ư��˥塼�˸���ޤ���ɡ��إ�ѥåɤ��ѻߤ��ƥ��ץ�������û������ϩ���ߤ������Τε�ư���֤Ȥ��ƻȤäƤ��ޤ��ʳ���ϩ��Ʃ�������Ƥ���Τǡ������ܤϥ���Ȥι������������褦�ʤ�Ρ�����åפؤ�ͶƳ�Ѥˡ��������饤�������Ƥ��ޤ��ˡ������������Ϥ�����ޤ��������ϥ���åפ�����Ǥ���
��������å�����λ�Ժ�����
������̹��ޥ�ʤΥ���åפ����������ϡ��䤿���������ʥ����˻Ȥ������ǡ����ǤϻԳ��ϤȤ��ư���졢UFO�Ƕ�Ť��Ƥߤ�ȡ������ȷ��ФˤʤäƤ��ޤ�����������ʬ��������ϡ�Boundary �ǰϤä���ʬ�ˤ�ʤ�äƤ��ޤ���ñ�ʤ�ʿ�Ϥˤʤ�ޤ��Τǡ����������Ϥ��鳰���ơ����ĥ��֥������ȤǺ�ä�����ȼ��̤��碌�����Ȥ����Ǥ���������������ˡ�Ǥϡ��Գ��ϥƥ�������Υӥ뤬���������ĤΥ������������̤ˤ�äơ�����åפ��ͤ��ˤäƤ��ޤ��ޤ���
����褹��ˤ�QJIS�ǡ��Գ��Ϥ����Ϥ��������ѹ�����Ф����ΤǤ������������Ǥ���ˡ��ʬ����ޤ��ʲ��������Ǥ����ĻԳ��ϤˤʤäƤ�����ʪ��ä��Ƥ��顢Ʊ��쥤�䡼������ϤΥݥꥴ�����������ʬ���ɲáפ�å����ơ��������ݥꥴ��ʥ���å���ʬ�ˤ��������Ф����ΤǤ��礦���ġ������줬ʬ����ȡ������Ω���ϤǤϸ��äƥӥ볹�ˤʤäƤ�����ʬ�ʼºݤ�¿�������ࡢ��ư��ˤ����Ϥʤɤ˽�ľ�����Ȥ����ơ����˽�����ΤǤ���������ν���Ǥ���
�����̤β����Ȥ��ƺ���ϼ·ʤΥ���å���ʬ��������Ϥ�ʤ�äƤ��ޤ�������Υ���åפ�˲����ͤ��Ф���ˡ��Τ�ޤ������ɤä��ߤ���åȥϡ��С�������Υ���åפϤ��ʤ극�Ф��ޤʤΤǡ�Ʊ�����֤ˤʤ��餫�ʿ�嵡�ѥ���åסʷ��У��١ˤ��֤��ȡ����������ͤ��Ф��ΤϤ������ʤ����ȤǤ���
���ͤ��Ф����ޤ���ˤϡ������Ϸ��Υ���å���ʬ���Τ�ä���Φ¦�ؿ������ޤ����⤢��ޤ���QJIS���Խ���������ʪ������Ǥ��顢�Ρ��ɥġ����Ȥä����Ǥ��ݤ��س�����Φ¦�˲����Ƥ���������ʪ���ѷ��פ����٤Ф����Τ��ʡ����������Ƥ��ޤ��ˡ��������������ȡ����ץ��������������������ʼ������Ǥϡ�����Φ���ݴɾ��ˤ������ʤꡢ���Τΰ����˻پ㤬�Фޤ��Τǡ����̤��Τޤޤˤ���Ĥ��Ǥ���
�����ޥ�ʾ����դ��Τ��줳�졧
������Ū�ʻ��ߤ����褿�Τǡ���åȥϡ��С��˸�����褦�����ߤ������ळ�Ȥˤ��ޤ������ǽ�ϡ��������ߤ����ʷ�ʪ���֤��н�ʬ���Ȼפä��ΤǤ���������ϼ̿��˻����ơ�����֥ϥ�����쥹�ȥ��ʤɣ���������ޯ���ʷ�ϵ������ä��Τ����䤿��˲������ä��������ꡢʣ���ʥ����ܤ�����ʪ�ǡ����ä����ĸ����ޤ��������������Ϥ��֤��Ƥߤ�ȡ������������ɤ�������Τǿ��ߤˤϤޤꡢ���Ω����־졢�ƥ˥������Ȥ��ä��ꡢ��åȤ��¤٤��ꤷ�ơ�Ȣ�����פ�ڤ��ߤޤ�������åȤ�ܡ��Ȥ���־�μ֤� FlightGear Scenery Website �������ꤷ�������ϲ�¤���ƻȤäƤ��ޤ���
����åȤ�α���뻷���ϡ�ñ��ʡ֥��פλ����ι�¤ʪ���äƺѤޤ��ޤ������Ȥ�����������Ϻ��ܤ�Φ�ߤˤ����ޤ������ᡢ����åɤʥ���ȹ�¤�˸����Ƥ��ޤ��ޤ�������åȤ�ܡ����Ѥϡ��������⤭������Ȥ��ޤ������꼰�λ����Ǥ��ȡ���Ĭ�����������̤���1��;�겼���äơ�������ʤ��ʤ뤫��Ǥ��������ǻ����κ��ܤ��ڤäƲ�ư�����֤�����ü���ʤɤ��礭�ʹ���¿�����֤��ޤ��������ι����⤭�������岼ư��ݤΥ��������ǡ��������Τ�ή�����Τ��ɤ���ޤ��������¿�����⤤�Ƥ��봶���פ˸����Ϥ�ޤ������Ĥޤ��������Ȥ�����ΤǤ��礦����(^^)��
��������ˤ��Ӥ��빽����Τǡ������Ƹ��������Ȼפ��ޤ�����FlightGear�μ��ڤϤ�¸���Τ褦�ˡ���ľ��Ω�ä�ʿ�̤�2��������ڤγ���Ž���դ��Ƥ���ޤ��������������100�ܤȤ��¤٤�Τϡ���֤�ե��������̤����ѤǤ��Τǡ��Ӥ餷��Ω�Τ��뤳�Ȥˤ��ޤ������빽���ơ�������ϤΥƥ��������Ž�ä����餤�Ǥϥ��ᡣAC3D�� Spike ��ǽ�ǥȥ��ȥ������䤷�Ƥ⡢�֥ȥ����������Фε�פˤ��������ޤ����פϡ�������Ū�ʵ�§�������äƤϤ����ʤ��ΤǤ��͡�
�������ǡ��������ӤĤˤ���Ⱦ����Ե�§�˽Ťͤ��¤٤ޤ������ƥ���������Լ�����ǻø���Фʤ��褦�����Τμ����ݤ��ˤ��ƶ���ʬ�����̤�����Τ����ġ�����ʤ�¿���ޥ��ʤ褦�Ǥ������������Ǥ��礦����
����ȯ�ʡ����μ��Ƥμºݡ�
���������ƿ�嵡�ǤΥޥ�ʤϽ��褿��ΤΡ��ºݤ�FlightGear��ǥ���åפ����Ѥ����硢��ǰ�ʤ���Ŭ�礹�뵡�郎�����ʤ�¤��뤳�Ȥ�ʬ����ޤ�����
���ޤ����Ф������������ޤ��ȡ���ư���ˡ�Osaka Hokkou Marina�פ���marina�ǽФޤ��ˡ�����ϩ01��19������������ץ���˵��Τ����줿�顢���������˱�äƲ�Ƭ��������åפ����äƿʿ夷�ޤ��ʥȡ���������Ϥ��ä���ľ�ʤ��ơ������������ǻߤޤäƥХå������ʿ夷�ޤ��ˡ���®�ǿ��Ť˿��������٤����������������դ��������ȥ�֥뤬�����ʤ��������Τˤ�ä�¿���ʤ�����ޤ���
���������ä��饮����夲�������ɤ���Ǽ���ξ��ϡ�L�ץ����Dz����ơ����νи��˸������ޤ��������졼������ꤷ�Ƥ��ޤ���������͡������Ծ�פγ���ϩ��ʿ�Ԥ������̤�Υ����Ӥȸ��ʤ��Ƥ��ޤ�������Ū�ˤϡ��ޥ�ʤ��������Ф�ȡ��ͤ�����������̤�Τ褦�ʴ����ǡ������˳��̤������äƤ��ޤ��Τǡ����ز�Ƭ���Ƽ�������250��270�٤��餤��Υ�夷�ޤ�������������ѤǤ��ˡ�
������ϥޥ�ʤ����������ɸ���ܶᤷ��������路�ƹ��������ޤ������İʾ������餫�˽����ۤɡ��������������Τ����Ѿ��ʤ��Τǡ������������������ü��ʬ�ʹ��ν�������ˤˡ�����Ƚ���������ץȤ�����ޤ����ʤɤ����ͤ�ȴ�����뤫�ϡ������åפ��Ƥ����ޤ����ΤǤ����Ȳ������ˡ�
�����ޤ���������ä��顢����åפ���������ä���®���ʡ����餫����ӡ���������Ф��Ƥ�������ä�����ߤ����Τޤ��Фäơ����ץ��������ޤ���
������åפ����Ѥ���ˤϡ����餫�Υӡ���������ɬ�פǤ������ؤʤ����Ͼ��ư�������嵡�ϡ����ߤǤ�¿���ĤäƤ��ޤ���������Ʊ�ͤ˵ʿ�ޤ�����Τ�������ޤ����͡�������HiTouch����Υ�������ʣ�յ��Τ褦�������æ��������Φξ�ѵ���Ȥ����Ȥˤʤ�ޤ����Ȥ��������Ǥ��ݤ䡢����åפȥ��ץ���ηѤ��ܤ��̲᤹��ݡ����Τ�˽��ƻ���Ƚ��ä��ꡢ�ե���������Τ�빽����ޤ����ƥ��Ȥǥ���åפ����ȯ��˰�������������ݤ˻Ĥä����Τ�Ƥ����ޤ���
�������������������
����¸������ꥫ����Ϸʼ���ѥ�����ɥ�ǥ��������դ��ڤ�ȡ���������β�ž�����Ѳ����������衼��ȯ�����뤿�ᡢ��®�ǤϾ���꤬�����ޤ�������٤Ϲ⤤��ΤΡ���������ƽ���������ǽ�Ǥ�������åפ���οʿ�ϥ��ࡼ���ǡ��ƾ�Φ�����ޤ����������θ奨�ץ���˰ܤ�ݤ˥��ߤޤꡢ�ƻ�ư�Ǥ��ʤ���礬�빽����ޤ��ʻ�ǰ�ʤ��鸶�������ˡ�
����DHC-3���å����ο�Φξ���ǡ�
���쥷�ץ�ñȯ�η�͢����ι�ҵ�������åפξ�겼��Ȥ��ʤ�̵������Ĥ�ڡ�ͣ�������ϡ����Ǿ���꤬�����ʤ����ȡ���������������ΰ�����������������ü�ն�ˤ��ͤ��ˤäƲ�������
�����ܥ�Х�ǥ���415��
�����ɿ�Ρ�����פ����롢�����ܥץ��å���ȯ���������Ͼ�ǤϾ���������ǽ�����Ǥ��ɤ��������夤������������ʻ�ѡʤޤ���ñ�Ȼ��ѡˤ���ȡ���ü�ե����Ȥ����ɤ��ʤ���ޤ�������åפ���οʿ�⥹�ࡼ�����������Ȥʤ��Τ褦�Ǥ����ĥ���åפ˺ƾ�Φ�������Ǥ��ݤǥե�������ʤ�����ޤ���
������줺�˿���Ĵ�٤��顢������åפ��ܿ�����ݤξ���Ѥ���줺������Ƚ������Ȥ�ʬ����ޤ������ʤ�С����å�������������кѤळ�ȤǤ����ʲ��β�¤��С��빽������ε��ΤȤʤ�ޤ���
����cl415-yasim.xml��
����spring-factor-not-planing�Ȥ���ʸ��������롣5���ꤢ�롣
������������ͤ���0.2�ס���0.9�פˤʤäƤ���Τǡ����٤ơ�2�פ˽����롣
������¸���롣
��;�̤ʤ�����ܵ������������Τ�������ϥ饤�ȥ֥롼����������ޤ���������ϥ��饤�֡����å��顼����������֥������ԥåȡ�������פ��о줹��Ͷ��δ�ģ��NUMA�סʹ�Ω���泤�ε��ءˤΥ��顼��餷���Ǥ���
���ʤ��ƻ��ߤδ���Ū�ʥƥ��Ȥˤϡ��䤬��ǯ���˲�¤���ƿ�嵡��������˻Ȥ������Ⱖ����Υԥ饿��PC��9M��Φξ�ѵ�����Ѥ��ޤ������ʳ�Φ�Ǿ���꤬���������ꤷ�ƿʿ塦��Φ����ǽ�Ǥ���
���������Ծ졧
����������������äȤ��Ҳ𤷤���������Ծ����ϤǤ����������Ǥϳ���ϩξü�����˼�������ơ���¦�ϡ֥���ե��˥ƥ��������åȡס���¦�ϱ�ư��ˤʤäƤ��ޤ����Ĥ�������ϸ��ߡ����ݡ��ĥ������ɡ����ι���פȸƤФ졢������Ҥ�ʿ�̿ޤˤ��ȳ���ϩ����25����ͶƳϩ�ʥ��ץ��ˤ���41���ǡ���Ĺ��410��������¸���Ƥ��ޤ���2003ǯ��������줿�̿��ˡ�����ϩ�ֹ��25�פξ�ǥХ�ɱ��դ���ͤ������̤äƤ��ޤ��Τǡ�����ϩ�Ϥ��������˰����������ΤΡ��ºݤϻȤ��Ƥ��ʤ��ä����Ȥ�ʬ����ޤ�����WED�Ǻ�ä�����ϩ���̤�06��24�ˤʤ�ޤ�������������07��25���������褦�Ǥ���
�����ʤ��ǡ��������礷�ޤ��ȡ��������Ծ��90ǯ�塢���ؤ���德�ױ�ư�Τ����˺��졢�����ߥʥ�ʤɤϷ��ߤ���ʤ��ޤޡ����٤Ⳬ�������˼��������Ϥޤä����ͤǤ������Ԥ��ܤΥ����Ȥˤ⡢�������Ƥλ����ϸ�������ޤ���Ǥ�����
���Ȥ⤢�졣�إ�ݡ��Ȥ��嵡�б��Υޥ�ʤȥ��åȤǻȤ��С�Φ���ˤޤ����������ʼ��������Ծ�ˤʤꤽ���Ǥ�����Ͽ̾�ϡ�Maishima Keihikoujyou�ס������ɤ�RJH03�ʼ����С������Ǥ�X������ޤ��͡ˤȤ��Ƽ���˼��ݤ���ޤ����������⤽�����ϩ����Ĺ���褯ʬ����ޤ��ͥåȤ�700����Ĥ��ޤ����������¤Ȥ��������û���Ǥ��͡����줳��פ���餷�ơ��ǽ�Ū�˻䤬�����WED������������ϩ����Ĺ785���Ǥ���������ä���ɤ����뤫���Τ�ޤ�������Ǥ�褷��Ĺ���ϻפ��ޤ���
���ۤ�̵���Ǽºݤ˾����������Ф��Ƥߤ�ȡ����Τ褦�����ӤǤ�����
����������172������ ����ϩĹ�Σ����Ȥä�ΥΦ����Φ���ϣ������ߡ�
�������å����������������Υ��Φ��
�����ܥ�Х�ǥ��������䶯��ΥΦ����������ߡ�
�����ԥ饿��PC��9M��ΥΦ�ϳ���ϩ����դ˻Ȥ��ڤꡢ���Ǥ�����ʤ���
�����å����ȥܥ�Х�ǥ���415��STOL���Ǥ����顢�ޤ�����ʤ�ΤǤ��礦������®�Υԥ饿��PC��9M�������ϡ��פä�����Ȥ̵꤬����ΥΦľ��ϥ���å�����������ͤ���㤯���ӡ��إ�ݡ��Ȥο���������300ft��Ķ���Ƥ����ޤ������ͤδ�������ۤɤǤϤ���ޤ�������Ū�ʤ�Ȥ�Ϥ��ޤ�ʤ���
�����ζ����ʣ���ζ����˶��USJ��ᤤ���ᡢVFR��������̲᤹��ȥ�ե��å����빽¿���Τ������Ǥ��������Ե����ѤȤʤ�ȡ��㤨�н鿴�Ԥ����������ˤ�ȯ�夹�뤳�Ȥ⤢�������Ǥ��礦���顢�����˶���Ŭ�Ϥ��ɤ�����������Ǥ����������dz�����碌���Τϡ�������������ä������Τ�ޤ���
�����������ߥ�졼������Ǥϡ�����ʶ�������ϩ����Ⱦ�̡��ȤƤ⿷���Ǥ������ʤβ��ۥե饤�Ȥϡ���ݶ�����3000�������ϩ��Ȥ����Ȥ�¿���ʤ꤬���Ǥ��Τǡ������������Ԥ�����ɤ�ʤ�Τ��������˵��ä��������ޤ�����
���ƥ������Ԥǰճ����ä��Τϡ���¦����Υ��ץ������Ǥ������Ծ����ϰ��̤�ʿ�Ϥǡ��·ʤǤϱ�ư��ȹ��ϤФ���Ǥ������ʤ��������ʥ����Իԥƥ������㡼��ʤ���Ƥ��ꡢPAPI�˽��äƹ߲���³����ȡ������������ˤ�뵿�����ĥӥ뤬���⤯�����ä������Ф˽����ޤ��������ǥ������˿��줽���ʵ�������ۤɤǡ����Ƥηи��Ǥ����Իԥƥ������㡼��������ϩ��ü�ޤ����äƤ��뤿�ᤫ���Τ�ޤ���
�������Хƥ������㡼��ĥ���ؤ������ΤǤ������������ǤϺ���ʤ��ᡢ�����Ծ�����ϡ����ϡˤ�����礭����ĥ���ơ��ӥ볹�γ������ޤ������������ƽ��褿�ˡ�WED������䥵�å����Υ��饦��ɤ�������Ŭ���˹��ϡ�Dry lakebed �� Gravel ��ɽ���ˤ�ä��ơ��·ʤ˻��������˻ž夲�ޤ���������Ǻ��Фϥԥ���ȼ��ޤꡢ��Ŭ�˥��ץ������Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
�����ȥ�ե��å����ѥ�����ˤĤ��ơ�
������Σ��������ߤؤΡ�������ϩ�ˤĤ��Ƥ��Ƥ����ޤ��礦����Ʋ����ˡ��ξ����ϩ�ޡפȤ���������夲�Ƥ����ޤ�����
���ޤ��إ�ݡ��Ȥ��顣
���������������Τ����ºݤ˻Ȥ��Ƥ���ȥ�ե��å����ѥ�����Ǥ�������1000ft�Ǽ����ѥ�����ؤν�����ϸѷ���ĺ����ʬ�ǹԤ��ޤ����إ�ѥåɤϰ�Ĥ����ǡ�������������Φ�ӣ����������̤Ǥ�RWY10�������ˤ������������������Φ�ӣ¡�Ʊ����RWY23�ˤ���Ĥ�Ťͤ����ˤʤäƤ��ޤ�������˹�碌�ƺǽ������쥰�⡢��¦���������¦�������Ĥ�����ޤ���
���إ�ѥåɤ�Ȭ�ѷ��������Ǥ����顢�ºݤ��᤹ܶ��ȡ��ɤθ�������������Ƥ����Τ��¤������Τ�ޤ������Գ���������������礬¿���Ȼפ��ޤ��������λ�����������ϸ��˸����������ߤ���ü�������Ȥ���إ�ݡ��Ȥؤθ��̤������ľ�ʤ���ȡ����������Ρ���Φ�ӣ¡פ����Ф��ޤ���
�����������Ծ졣
���������ȥ�ե��å����ѥ�����ǡ��������ʤ����Ἣʬ�ǹͤ��ޤ�����û�դ�Ĺ����nm��Ĺ�դϳ���ϩ���������nm����Ĺ���ˤ��Ƥ��ޤ���ɸ������ǤϤ��Ĥ��Τǡ������ߤǹ����Ʋ����äƷ빽�Ǥ�������ϩ��ξü�˿ή����PAPI�����ꡢ����ˤ���Ĺ2ʬ��1�Υޡ���������3�ܡˤ�����ޤ��������Υޡ����Τ��Фˤ�ABN������ޤ����������ߤȸƤ٤��Τϡ���������Ǥ���
�������Ծ�˥��ץ���������ˤϡ������濴������ϡ���Ϥ��������˽Ф�Τ���ñ�Ǥ������߱褤�˲ϸ��ؿʤ�ȡ��ۤ����̤˳���ϩ�������Ȥ��ޤ�����¦����Ǥ��ȡ����Ͷ���VOR��111.25KCE�ˤΥ����ȥХ���ɥ饸����83�٤˾�ä���8nm���ʡ�����ϩ�θ��̤�����˽Ф��顢�����������ؽ����ɤ���ޤ���
���Ǹ������̹��ޥ�ʡ�
�������졼����ä����ꤷ�Ƥ��ޤ�����������ǰϤޤ줿�������Ⱦʬ�����������˻ȤäƤ��ޤ������̤�ȯ�夹��ȡ���¦�δߤ����ϤΤ��ᡢ�פ�������Φ���ܶᤷ��붲�줬����ޤ���������Τ������Ф���ʬ�ϡ����ͤ��Ƥ�������ͤ�ȴ�������֤Ǥ�������ؤν����꤬�����ϡ��������ͤ��ˤäƤ���ޤ���
������ꤢ�����������Ǥ���
���Ĥޤ��ޤ����ɤ�;�Ϥ�����Ȼפ��ޤ������ҤȤޤ������ȸ��ʤ��ơ������ʥ�ΰ��̥ǡ������JA���؎��ގŎَ��ގ��ݎێ��ĎޡפˤƸ���������ĺ���ޤ����Ȥ����ϰʲ����̤�Ǥ���
����Maishima-fg-CustomScenery.zip �����������ɤ��Ʋ��ष��
����Ǥ�դΥ������ॷ���ʥ�ѥե������Ǽ��ơ�
����FlightGear�ε�ư���̡�Add-ons�פ�å���
�������־�˸��줿��Additional scenery locations�ץ�����ɥ��α��ˤ���
�����֡ܡץܥ����å����ơ�Maishima-fg-CustomScenery�ե���������롣
����������inomaty����Ρ�Kansai-fg-CustomScenery-master�פ�Ʊ�����Ѥ������ϡ�
��Kansai-fg-CustomScenery-master\Terrain\e130n30\e135n34�ե���������äƤ��롢
��5168937.btg.gz��5168937.stg��ɬ���̤ξ������Ʋ�������
��Maishima�����ʥ����Ͽ���ɬ��Kansai�����ʥ���Ⲽ�ˤ��Ƥ���������
���ʾ����Ԥ��ʤ���硢��δĶ��Ǥ�ɽ���۾郎ȯ�����ޤ���
������ϥإ�ݡ��ȼ��դ�����ߡ���¦���дߤˤ����åȥϡ��С�������̹��ޥ�ʡפ䡢���Ĥƥإ�ݡ��Ȥ�����¤��줿�������Ծ�פ�Ƹ����뤪�äǤ������������ʥ�� Maishima-fg-CustomScenery �Ȥ��ơ�JP���؎��ގŎَ��ގ��ݎێ��Ďޤ˥��åפ�����ĺ���ޤ������ʤ�����ĺ������ϡ�ʸ����������ɬ��������������
�����Ҹ˷��䶶���롧
�����������إ�ݡ��Ȥ�����������ΤΡ����θ���ӥ�R44��EC135P2��ȯ��ƥ��Ȥ�Ťͤ��Ȥ������ɤ���̿��Ǹ����·ʤ�ʷ�ϵ����㤦�����Ȥ������ݤ�����ޤ�����
����90ǯ�塢����ϸ��Τ������˽��褿���Ω���Ϥǡ�����Ͷ�פ�ƨ���ưʹߡ������Τ�����Ǥ���ä���ʤ��¤ꡢ����ޤ�����λȤ�ƻ��̵�������Ǥ������ߤ�����ʬ���Ƽ殺�饦��ɤ���ࡢ���Ϥ�ʤ���Ƥ��ޤ�������¦�Υإ�ݡ����ն�������㳰�ǡ�����ͤ��������å������ʲ����ť������ˤ䡢�����ʪή�����������ޤäƤ��ޤ������äƥإ�Υ��ץ�������볦�ˤϡ�����ʤ�����¤�����櫓�ǡ�¿���Ϸ�ʪ��Ƹ����ʤ��ȡ��ºݤȤ���Υ�줿���Ծ��ˤʤäƤ��ޤ��ޤ���
���Ĥ����ǥ���ץ�ʤ��顢���狼�ӥ����ޤ�������Ϥ�ϡ��䤿�����Ω�ı�ť�����졣�ּ�������ľ���Ϥʤ����פ������ʤޤ�ǥ���ȥ˥��������ǥ��ˤȤ������������ȥꥢ�η��۲Ȥκ�ǡ��̿��Ǹ���¤�ϡ����ɼ�ʥơ��ޥѡ����Ȥ����פ��ޤ����Ѥ���1�ܤޤǡ������ϥȥ���ޤǶŤäƤ��뤽���ǡ�������Ƕ�Τ����ޤꡣ������Ȥ��꤬�ʤ��Τ�ñ���Ȣ���ˤ��ơ��⤵120���Ȥ������ͤζ��å����Υ����ʬ�����ϡ�������������ȤäƤ���餷�����餻�ޤ�����
�����Υӥ��ǡ�������֤����Ȥ������֤���㡢���ä����Ť��ʤ��ʤ��פȼ´������Ծ����Ѳ���ȩ�Ǵ������ޤ������ޤ��������Ǥ��������Ƕ��٤�ʪή�Ҹˤ⣳��ۤ������������ϴ�ά�������ȥ�å�����겼�ꤹ����פ���ñ��ʱ����ǺƸ����ơ����Ϥμ̿���į��ʤ���ƥ�������������ޤ�����
�������η�ʪ���¤٤�ȡ��ޤ��ޤ����Ω���Ϥ餷���ʤäƤ��ޤ�����Ʊ���ʹԤǥ�åȥϡ��С����äƤ����Τǡ��ϡ��С��ȥ���å��������ּ�ĥ���־���綶�פ��ߤ����ʤ�ޤ�������ʹ⤵��90���ˤϰ��ܤʤΤ����Ū���䤹�����Ǥ��������夬��̯�˾岼��ȿ�äơ����ޤ��˥����֤��Ƥ��ޤ�������ʤ�Τϡ��ɤ���������Ф����ΤǤ��礦���ġ�
���ͥåȤ�õ����ä��鹬���ˤ⡢������λ��̿ޤ����Ĥ���ޤ�������������ˣ������ζ�������Ե���ƹ�Τ�����¤��Τ�Ʊ���ֲ����Ф��פε�ˡ����������гھ��ĤȻפä��ΤǤ������̾��̤�1�ѡ�1�ԥ�����Dz������ä��Ȥ������礭������AC3D���ɤ�Ǥ���ޤ���10ʬ��1�˽̾����ƺ�Ȥ˳ݤ���ޤ�����
�������������ξ¦�ز����Ф���ʤᡢ��ƻ�ϥ����ե���ȳ���ϩ�Υƥ��������Ž�äơ���ƻ��ʬ��·ʤ�Ʊ���Ф��忧�����ȤϺ����褯������ȶ���δ֤Υ磻���ĥ�äƤ����д����Ǥ�����Ȥ���UFO�Ǹ�������֤����Ȥ������������ĥ�������10ʬ��1�ΤޤޤǤ���(^^;)��
��3��������1000��γ����ݤ��ƺ����֡��֤ʤ��UFO���Ϥ�����Ȥ������ʤ�ˤĤ�������Υ磻�䷲���·��̤ꡢƬ��ؤ��ꤸ������;��˹����äƸ������ʤ��ʤ����㤷�ޤ�����
�����ޥ�ʤμ���ϥ����졼�إ�ѥåɡ��������ϩ����
�������ϥإ�ݡ��Ȥ��дߤˤ��롢����̹��ʤۤä����˥ޥ�ʤ��������ޤ�������⾯������ޤ�������ɸ��ǡ����˸����Τ���ӥ볹��ʿ������Ϥ���ƥ��Ȥȡ��緿�Υ���åפ���Ѥ��ƿ�嵡���Ϥˤ��Ƥߤ褦���Ȥ����Τ���Ū�Ǥ�����ϰ��������Ͷ���������˥���åפ��Ǽ�ˤ��ߤ��������Ѥο�嵡���Ϥˤ�����ɤ����ȶ��ۤ��Ƥ��ޤ����������������ȶ����˲Ͷ��λ��ߤ��դ������ϡ��ºߤΥ�åȥϡ��С������Ѥ��ƿ�嵡���Ѥ�����������ʤ褦�˻פ��ޤ����ʤ�к��إ�ݡ��Ȥȥ��åȤǺ�äƤ��ޤ������Ȥ����櫓�Ǥ���
���ǽ�ϥإ�ݡ��Ȥ�WED�ǡ����ˡ������ϡפȤ��ơ�Boundary�⡼�ɤǥޥ�����Ϥ����������ΤǤ������ƥ����ѥ����ʥ��ư���Ƥߤ�ȡ��ʤ����إ�ݡ��Ȥ����Ϥ������Ф����������������������ߥʥ�ӥ���Ǽ�ˤ�����⤤�Ƥ��ޤ��ޤ�����������������ɸ��˱ƶ����Ф�褦�Ǥ��������ǥޥ�ʤϥץ������塢��Ω���������Ȥ��ƺ��ľ�����Ȥˤ��ޤ��������������פ�Seaport�Ǥ���
�����ۤ�ICAO�����ɡ�RJH02�פ�Ϳ���ơʸ������Ǥϡ��ޤ���X�פ��դ��Ƥ��ޤ��ˡ����̤����ݥå������û�������졼��ʳ����ӡˤ����ꡣ�����ǵ��Τ�ư�����Ƴ����ޤǥ���������Υ�������Ԥ��Ĥ��Ǥ����Ȥ����������졼������ꤹ��ȡ��ʤ�����ɽ�Υƥ������㤬�ӥ�ӥ꿶ư����ʤɡ�ɽ���ȥ�֥뤬³���ޤ������ºݤα��ѻ��ϡ���Ͽ�嵡���Ͼ�ǵ�ư���ƥ���åפ��鳤�˹ߤ����������⤹��Φ�Ȥ�����Ĥ��ʼ��������������Ʊ���ˤǤ��Τǡ������Ͽ��ǵ�ư���뵡ǽ�����פǤ��������ǥ����졼����ơ����ץ������������������˥إ�ѥåɤ��ߤ����Ȥ���������˲���ɽ�������褦�ˤʤ�ޤ����ʳ���ϩ�������졼�إ�ѥåɤ�����Ĥ��ߤ��ʤ��ȡ�WED�����顼��Ф��ޤ��ˡ�
�����Τ��ȡ������졼��ȥإ�ݡ��Ȥ�ʻ�Ѥ��ޤ����������������פˤ�äơ������줫����������ư��˥塼�˸���ޤ���ɡ��إ�ѥåɤ��ѻߤ��ƥ��ץ�������û������ϩ���ߤ������Τε�ư���֤Ȥ��ƻȤäƤ��ޤ��ʳ���ϩ��Ʃ�������Ƥ���Τǡ������ܤϥ���Ȥι������������褦�ʤ�Ρ�����åפؤ�ͶƳ�Ѥˡ��������饤�������Ƥ��ޤ��ˡ������������Ϥ�����ޤ��������ϥ���åפ�����Ǥ���
��������å�����λ�Ժ�����
������̹��ޥ�ʤΥ���åפ����������ϡ��䤿���������ʥ����˻Ȥ������ǡ����ǤϻԳ��ϤȤ��ư���졢UFO�Ƕ�Ť��Ƥߤ�ȡ������ȷ��ФˤʤäƤ��ޤ�����������ʬ��������ϡ�Boundary �ǰϤä���ʬ�ˤ�ʤ�äƤ��ޤ���ñ�ʤ�ʿ�Ϥˤʤ�ޤ��Τǡ����������Ϥ��鳰���ơ����ĥ��֥������ȤǺ�ä�����ȼ��̤��碌�����Ȥ����Ǥ���������������ˡ�Ǥϡ��Գ��ϥƥ�������Υӥ뤬���������ĤΥ������������̤ˤ�äơ�����åפ��ͤ��ˤäƤ��ޤ��ޤ���
����褹��ˤ�QJIS�ǡ��Գ��Ϥ����Ϥ��������ѹ�����Ф����ΤǤ������������Ǥ���ˡ��ʬ����ޤ��ʲ��������Ǥ����ĻԳ��ϤˤʤäƤ�����ʪ��ä��Ƥ��顢Ʊ��쥤�䡼������ϤΥݥꥴ�����������ʬ���ɲáפ�å����ơ��������ݥꥴ��ʥ���å���ʬ�ˤ��������Ф����ΤǤ��礦���ġ������줬ʬ����ȡ������Ω���ϤǤϸ��äƥӥ볹�ˤʤäƤ�����ʬ�ʼºݤ�¿�������ࡢ��ư��ˤ����Ϥʤɤ˽�ľ�����Ȥ����ơ����˽�����ΤǤ���������ν���Ǥ���
�����̤β����Ȥ��ƺ���ϼ·ʤΥ���å���ʬ��������Ϥ�ʤ�äƤ��ޤ�������Υ���åפ�˲����ͤ��Ф���ˡ��Τ�ޤ������ɤä��ߤ���åȥϡ��С�������Υ���åפϤ��ʤ극�Ф��ޤʤΤǡ�Ʊ�����֤ˤʤ��餫�ʿ�嵡�ѥ���åסʷ��У��١ˤ��֤��ȡ����������ͤ��Ф��ΤϤ������ʤ����ȤǤ���
���ͤ��Ф����ޤ���ˤϡ������Ϸ��Υ���å���ʬ���Τ�ä���Φ¦�ؿ������ޤ����⤢��ޤ���QJIS���Խ���������ʪ������Ǥ��顢�Ρ��ɥġ����Ȥä����Ǥ��ݤ��س�����Φ¦�˲����Ƥ���������ʪ���ѷ��פ����٤Ф����Τ��ʡ����������Ƥ��ޤ��ˡ��������������ȡ����ץ��������������������ʼ������Ǥϡ�����Φ���ݴɾ��ˤ������ʤꡢ���Τΰ����˻پ㤬�Фޤ��Τǡ����̤��Τޤޤˤ���Ĥ��Ǥ���
�����ޥ�ʾ����դ��Τ��줳�졧
������Ū�ʻ��ߤ����褿�Τǡ���åȥϡ��С��˸�����褦�����ߤ������ळ�Ȥˤ��ޤ������ǽ�ϡ��������ߤ����ʷ�ʪ���֤��н�ʬ���Ȼפä��ΤǤ���������ϼ̿��˻����ơ�����֥ϥ�����쥹�ȥ��ʤɣ���������ޯ���ʷ�ϵ������ä��Τ����䤿��˲������ä��������ꡢʣ���ʥ����ܤ�����ʪ�ǡ����ä����ĸ����ޤ��������������Ϥ��֤��Ƥߤ�ȡ������������ɤ�������Τǿ��ߤˤϤޤꡢ���Ω����־졢�ƥ˥������Ȥ��ä��ꡢ��åȤ��¤٤��ꤷ�ơ�Ȣ�����פ�ڤ��ߤޤ�������åȤ�ܡ��Ȥ���־�μ֤� FlightGear Scenery Website �������ꤷ�������ϲ�¤���ƻȤäƤ��ޤ���
����åȤ�α���뻷���ϡ�ñ��ʡ֥��פλ����ι�¤ʪ���äƺѤޤ��ޤ������Ȥ�����������Ϻ��ܤ�Φ�ߤˤ����ޤ������ᡢ����åɤʥ���ȹ�¤�˸����Ƥ��ޤ��ޤ�������åȤ�ܡ����Ѥϡ��������⤭������Ȥ��ޤ������꼰�λ����Ǥ��ȡ���Ĭ�����������̤���1��;�겼���äơ�������ʤ��ʤ뤫��Ǥ��������ǻ����κ��ܤ��ڤäƲ�ư�����֤�����ü���ʤɤ��礭�ʹ���¿�����֤��ޤ��������ι����⤭�������岼ư��ݤΥ��������ǡ��������Τ�ή�����Τ��ɤ���ޤ��������¿�����⤤�Ƥ��봶���פ˸����Ϥ�ޤ������Ĥޤ��������Ȥ�����ΤǤ��礦����(^^)��
��������ˤ��Ӥ��빽����Τǡ������Ƹ��������Ȼפ��ޤ�����FlightGear�μ��ڤϤ�¸���Τ褦�ˡ���ľ��Ω�ä�ʿ�̤�2��������ڤγ���Ž���դ��Ƥ���ޤ��������������100�ܤȤ��¤٤�Τϡ���֤�ե��������̤����ѤǤ��Τǡ��Ӥ餷��Ω�Τ��뤳�Ȥˤ��ޤ������빽���ơ�������ϤΥƥ��������Ž�ä����餤�Ǥϥ��ᡣAC3D�� Spike ��ǽ�ǥȥ��ȥ������䤷�Ƥ⡢�֥ȥ����������Фε�פˤ��������ޤ����פϡ�������Ū�ʵ�§�������äƤϤ����ʤ��ΤǤ��͡�
�������ǡ��������ӤĤˤ���Ⱦ����Ե�§�˽Ťͤ��¤٤ޤ������ƥ���������Լ�����ǻø���Фʤ��褦�����Τμ����ݤ��ˤ��ƶ���ʬ�����̤�����Τ����ġ�����ʤ�¿���ޥ��ʤ褦�Ǥ������������Ǥ��礦����
����ȯ�ʡ����μ��Ƥμºݡ�
���������ƿ�嵡�ǤΥޥ�ʤϽ��褿��ΤΡ��ºݤ�FlightGear��ǥ���åפ����Ѥ����硢��ǰ�ʤ���Ŭ�礹�뵡�郎�����ʤ�¤��뤳�Ȥ�ʬ����ޤ�����
���ޤ����Ф������������ޤ��ȡ���ư���ˡ�Osaka Hokkou Marina�פ���marina�ǽФޤ��ˡ�����ϩ01��19������������ץ���˵��Τ����줿�顢���������˱�äƲ�Ƭ��������åפ����äƿʿ夷�ޤ��ʥȡ���������Ϥ��ä���ľ�ʤ��ơ������������ǻߤޤäƥХå������ʿ夷�ޤ��ˡ���®�ǿ��Ť˿��������٤����������������դ��������ȥ�֥뤬�����ʤ��������Τˤ�ä�¿���ʤ�����ޤ���
���������ä��饮����夲�������ɤ���Ǽ���ξ��ϡ�L�ץ����Dz����ơ����νи��˸������ޤ��������졼������ꤷ�Ƥ��ޤ���������͡������Ծ�פγ���ϩ��ʿ�Ԥ������̤�Υ����Ӥȸ��ʤ��Ƥ��ޤ�������Ū�ˤϡ��ޥ�ʤ��������Ф�ȡ��ͤ�����������̤�Τ褦�ʴ����ǡ������˳��̤������äƤ��ޤ��Τǡ����ز�Ƭ���Ƽ�������250��270�٤��餤��Υ�夷�ޤ�������������ѤǤ��ˡ�
������ϥޥ�ʤ����������ɸ���ܶᤷ��������路�ƹ��������ޤ������İʾ������餫�˽����ۤɡ��������������Τ����Ѿ��ʤ��Τǡ������������������ü��ʬ�ʹ��ν�������ˤˡ�����Ƚ���������ץȤ�����ޤ����ʤɤ����ͤ�ȴ�����뤫�ϡ������åפ��Ƥ����ޤ����ΤǤ����Ȳ������ˡ�
�����ޤ���������ä��顢����åפ���������ä���®���ʡ����餫����ӡ���������Ф��Ƥ�������ä�����ߤ����Τޤ��Фäơ����ץ��������ޤ���
������åפ����Ѥ���ˤϡ����餫�Υӡ���������ɬ�פǤ������ؤʤ����Ͼ��ư�������嵡�ϡ����ߤǤ�¿���ĤäƤ��ޤ���������Ʊ�ͤ˵ʿ�ޤ�����Τ�������ޤ����͡�������HiTouch����Υ�������ʣ�յ��Τ褦�������æ��������Φξ�ѵ���Ȥ����Ȥˤʤ�ޤ����Ȥ��������Ǥ��ݤ䡢����åפȥ��ץ���ηѤ��ܤ��̲᤹��ݡ����Τ�˽��ƻ���Ƚ��ä��ꡢ�ե���������Τ�빽����ޤ����ƥ��Ȥǥ���åפ����ȯ��˰�������������ݤ˻Ĥä����Τ�Ƥ����ޤ���
�������������������
����¸������ꥫ����Ϸʼ���ѥ�����ɥ�ǥ��������դ��ڤ�ȡ���������β�ž�����Ѳ����������衼��ȯ�����뤿�ᡢ��®�ǤϾ���꤬�����ޤ�������٤Ϲ⤤��ΤΡ���������ƽ���������ǽ�Ǥ�������åפ���οʿ�ϥ��ࡼ���ǡ��ƾ�Φ�����ޤ����������θ奨�ץ���˰ܤ�ݤ˥��ߤޤꡢ�ƻ�ư�Ǥ��ʤ���礬�빽����ޤ��ʻ�ǰ�ʤ��鸶�������ˡ�
����DHC-3���å����ο�Φξ���ǡ�
���쥷�ץ�ñȯ�η�͢����ι�ҵ�������åפξ�겼��Ȥ��ʤ�̵������Ĥ�ڡ�ͣ�������ϡ����Ǿ���꤬�����ʤ����ȡ���������������ΰ�����������������ü�ն�ˤ��ͤ��ˤäƲ�������
�����ܥ�Х�ǥ���415��
�����ɿ�Ρ�����פ����롢�����ܥץ��å���ȯ���������Ͼ�ǤϾ���������ǽ�����Ǥ��ɤ��������夤������������ʻ�ѡʤޤ���ñ�Ȼ��ѡˤ���ȡ���ü�ե����Ȥ����ɤ��ʤ���ޤ�������åפ���οʿ�⥹�ࡼ�����������Ȥʤ��Τ褦�Ǥ����ĥ���åפ˺ƾ�Φ�������Ǥ��ݤǥե�������ʤ�����ޤ���
������줺�˿���Ĵ�٤��顢������åפ��ܿ�����ݤξ���Ѥ���줺������Ƚ������Ȥ�ʬ����ޤ������ʤ�С����å�������������кѤळ�ȤǤ����ʲ��β�¤��С��빽������ε��ΤȤʤ�ޤ���
����cl415-yasim.xml��
����spring-factor-not-planing�Ȥ���ʸ��������롣5���ꤢ�롣
������������ͤ���0.2�ס���0.9�פˤʤäƤ���Τǡ����٤ơ�2�פ˽����롣
������¸���롣
��;�̤ʤ�����ܵ������������Τ�������ϥ饤�ȥ֥롼����������ޤ���������ϥ��饤�֡����å��顼����������֥������ԥåȡ�������פ��о줹��Ͷ��δ�ģ��NUMA�סʹ�Ω���泤�ε��ءˤΥ��顼��餷���Ǥ���
���ʤ��ƻ��ߤδ���Ū�ʥƥ��Ȥˤϡ��䤬��ǯ���˲�¤���ƿ�嵡��������˻Ȥ������Ⱖ����Υԥ饿��PC��9M��Φξ�ѵ�����Ѥ��ޤ������ʳ�Φ�Ǿ���꤬���������ꤷ�ƿʿ塦��Φ����ǽ�Ǥ���
���������Ծ졧
����������������äȤ��Ҳ𤷤���������Ծ����ϤǤ����������Ǥϳ���ϩξü�����˼�������ơ���¦�ϡ֥���ե��˥ƥ��������åȡס���¦�ϱ�ư��ˤʤäƤ��ޤ����Ĥ�������ϸ��ߡ����ݡ��ĥ������ɡ����ι���פȸƤФ졢������Ҥ�ʿ�̿ޤˤ��ȳ���ϩ����25����ͶƳϩ�ʥ��ץ��ˤ���41���ǡ���Ĺ��410��������¸���Ƥ��ޤ���2003ǯ��������줿�̿��ˡ�����ϩ�ֹ��25�פξ�ǥХ�ɱ��դ���ͤ������̤äƤ��ޤ��Τǡ�����ϩ�Ϥ��������˰����������ΤΡ��ºݤϻȤ��Ƥ��ʤ��ä����Ȥ�ʬ����ޤ�����WED�Ǻ�ä�����ϩ���̤�06��24�ˤʤ�ޤ�������������07��25���������褦�Ǥ���
�����ʤ��ǡ��������礷�ޤ��ȡ��������Ծ��90ǯ�塢���ؤ���德�ױ�ư�Τ����˺��졢�����ߥʥ�ʤɤϷ��ߤ���ʤ��ޤޡ����٤Ⳬ�������˼��������Ϥޤä����ͤǤ������Ԥ��ܤΥ����Ȥˤ⡢�������Ƥλ����ϸ�������ޤ���Ǥ�����
���Ȥ⤢�졣�إ�ݡ��Ȥ��嵡�б��Υޥ�ʤȥ��åȤǻȤ��С�Φ���ˤޤ����������ʼ��������Ծ�ˤʤꤽ���Ǥ�����Ͽ̾�ϡ�Maishima Keihikoujyou�ס������ɤ�RJH03�ʼ����С������Ǥ�X������ޤ��͡ˤȤ��Ƽ���˼��ݤ���ޤ����������⤽�����ϩ����Ĺ���褯ʬ����ޤ��ͥåȤ�700����Ĥ��ޤ����������¤Ȥ��������û���Ǥ��͡����줳��פ���餷�ơ��ǽ�Ū�˻䤬�����WED������������ϩ����Ĺ785���Ǥ���������ä���ɤ����뤫���Τ�ޤ�������Ǥ�褷��Ĺ���ϻפ��ޤ���
���ۤ�̵���Ǽºݤ˾����������Ф��Ƥߤ�ȡ����Τ褦�����ӤǤ�����
����������172������ ����ϩĹ�Σ����Ȥä�ΥΦ����Φ���ϣ������ߡ�
�������å����������������Υ��Φ��
�����ܥ�Х�ǥ��������䶯��ΥΦ����������ߡ�
�����ԥ饿��PC��9M��ΥΦ�ϳ���ϩ����դ˻Ȥ��ڤꡢ���Ǥ�����ʤ���
�����å����ȥܥ�Х�ǥ���415��STOL���Ǥ����顢�ޤ�����ʤ�ΤǤ��礦������®�Υԥ饿��PC��9M�������ϡ��פä�����Ȥ̵꤬����ΥΦľ��ϥ���å�����������ͤ���㤯���ӡ��إ�ݡ��Ȥο���������300ft��Ķ���Ƥ����ޤ������ͤδ�������ۤɤǤϤ���ޤ�������Ū�ʤ�Ȥ�Ϥ��ޤ�ʤ���
�����ζ����ʣ���ζ����˶��USJ��ᤤ���ᡢVFR��������̲᤹��ȥ�ե��å����빽¿���Τ������Ǥ��������Ե����ѤȤʤ�ȡ��㤨�н鿴�Ԥ����������ˤ�ȯ�夹�뤳�Ȥ⤢�������Ǥ��礦���顢�����˶���Ŭ�Ϥ��ɤ�����������Ǥ����������dz�����碌���Τϡ�������������ä������Τ�ޤ���
�����������ߥ�졼������Ǥϡ�����ʶ�������ϩ����Ⱦ�̡��ȤƤ⿷���Ǥ������ʤβ��ۥե饤�Ȥϡ���ݶ�����3000�������ϩ��Ȥ����Ȥ�¿���ʤ꤬���Ǥ��Τǡ������������Ԥ�����ɤ�ʤ�Τ��������˵��ä��������ޤ�����
���ƥ������Ԥǰճ����ä��Τϡ���¦����Υ��ץ������Ǥ������Ծ����ϰ��̤�ʿ�Ϥǡ��·ʤǤϱ�ư��ȹ��ϤФ���Ǥ������ʤ��������ʥ����Իԥƥ������㡼��ʤ���Ƥ��ꡢPAPI�˽��äƹ߲���³����ȡ������������ˤ�뵿�����ĥӥ뤬���⤯�����ä������Ф˽����ޤ��������ǥ������˿��줽���ʵ�������ۤɤǡ����Ƥηи��Ǥ����Իԥƥ������㡼��������ϩ��ü�ޤ����äƤ��뤿�ᤫ���Τ�ޤ���
�������Хƥ������㡼��ĥ���ؤ������ΤǤ������������ǤϺ���ʤ��ᡢ�����Ծ�����ϡ����ϡˤ�����礭����ĥ���ơ��ӥ볹�γ������ޤ������������ƽ��褿�ˡ�WED������䥵�å����Υ��饦��ɤ�������Ŭ���˹��ϡ�Dry lakebed �� Gravel ��ɽ���ˤ�ä��ơ��·ʤ˻��������˻ž夲�ޤ���������Ǻ��Фϥԥ���ȼ��ޤꡢ��Ŭ�˥��ץ������Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
�����ȥ�ե��å����ѥ�����ˤĤ��ơ�
������Σ��������ߤؤΡ�������ϩ�ˤĤ��Ƥ��Ƥ����ޤ��礦����Ʋ����ˡ��ξ����ϩ�ޡפȤ���������夲�Ƥ����ޤ�����
���ޤ��إ�ݡ��Ȥ��顣
���������������Τ����ºݤ˻Ȥ��Ƥ���ȥ�ե��å����ѥ�����Ǥ�������1000ft�Ǽ����ѥ�����ؤν�����ϸѷ���ĺ����ʬ�ǹԤ��ޤ����إ�ѥåɤϰ�Ĥ����ǡ�������������Φ�ӣ����������̤Ǥ�RWY10�������ˤ������������������Φ�ӣ¡�Ʊ����RWY23�ˤ���Ĥ�Ťͤ����ˤʤäƤ��ޤ�������˹�碌�ƺǽ������쥰�⡢��¦���������¦�������Ĥ�����ޤ���
���إ�ѥåɤ�Ȭ�ѷ��������Ǥ����顢�ºݤ��᤹ܶ��ȡ��ɤθ�������������Ƥ����Τ��¤������Τ�ޤ������Գ���������������礬¿���Ȼפ��ޤ��������λ�����������ϸ��˸����������ߤ���ü�������Ȥ���إ�ݡ��Ȥؤθ��̤������ľ�ʤ���ȡ����������Ρ���Φ�ӣ¡פ����Ф��ޤ���
�����������Ծ졣
���������ȥ�ե��å����ѥ�����ǡ��������ʤ����Ἣʬ�ǹͤ��ޤ�����û�դ�Ĺ����nm��Ĺ�դϳ���ϩ���������nm����Ĺ���ˤ��Ƥ��ޤ���ɸ������ǤϤ��Ĥ��Τǡ������ߤǹ����Ʋ����äƷ빽�Ǥ�������ϩ��ξü�˿ή����PAPI�����ꡢ����ˤ���Ĺ2ʬ��1�Υޡ���������3�ܡˤ�����ޤ��������Υޡ����Τ��Фˤ�ABN������ޤ����������ߤȸƤ٤��Τϡ���������Ǥ���
�������Ծ�˥��ץ���������ˤϡ������濴������ϡ���Ϥ��������˽Ф�Τ���ñ�Ǥ������߱褤�˲ϸ��ؿʤ�ȡ��ۤ����̤˳���ϩ�������Ȥ��ޤ�����¦����Ǥ��ȡ����Ͷ���VOR��111.25KCE�ˤΥ����ȥХ���ɥ饸����83�٤˾�ä���8nm���ʡ�����ϩ�θ��̤�����˽Ф��顢�����������ؽ����ɤ���ޤ���
���Ǹ������̹��ޥ�ʡ�
�������졼����ä����ꤷ�Ƥ��ޤ�����������ǰϤޤ줿�������Ⱦʬ�����������˻ȤäƤ��ޤ������̤�ȯ�夹��ȡ���¦�δߤ����ϤΤ��ᡢ�פ�������Φ���ܶᤷ��붲�줬����ޤ���������Τ������Ф���ʬ�ϡ����ͤ��Ƥ�������ͤ�ȴ�������֤Ǥ�������ؤν����꤬�����ϡ��������ͤ��ˤäƤ���ޤ���
������ꤢ�����������Ǥ���
���Ĥޤ��ޤ����ɤ�;�Ϥ�����Ȼפ��ޤ������ҤȤޤ������ȸ��ʤ��ơ������ʥ�ΰ��̥ǡ������JA���؎��ގŎَ��ގ��ݎێ��ĎޡפˤƸ���������ĺ���ޤ����Ȥ����ϰʲ����̤�Ǥ���
����Maishima-fg-CustomScenery.zip �����������ɤ��Ʋ��ष��
����Ǥ�դΥ������ॷ���ʥ�ѥե������Ǽ��ơ�
����FlightGear�ε�ư���̡�Add-ons�פ�å���
�������־�˸��줿��Additional scenery locations�ץ�����ɥ��α��ˤ���
�����֡ܡץܥ����å����ơ�Maishima-fg-CustomScenery�ե���������롣
����������inomaty����Ρ�Kansai-fg-CustomScenery-master�פ�Ʊ�����Ѥ������ϡ�
��Kansai-fg-CustomScenery-master\Terrain\e130n30\e135n34�ե���������äƤ��롢
��5168937.btg.gz��5168937.stg��ɬ���̤ξ������Ʋ�������
��Maishima�����ʥ����Ͽ���ɬ��Kansai�����ʥ���Ⲽ�ˤ��Ƥ���������
���ʾ����Ԥ��ʤ���硢��δĶ��Ǥ�ɽ���۾郎ȯ�����ޤ���
��ɼ��:25
ʿ����:6.00
inomaty
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
����Ф�ϡ�hide����inomaty�Ǥ���
��®����������ɤ����Ƥ������������˥���åפǿ�Φξ�ѵ���ͷ�Ф����Ƥ��������ޤ������������������桹̵���ΤǤ����Ǥ��͡�����å����������綶�⤢�ä���Ũ�Ǥ���
�ܲȥե�������Ʊ���褦���㤬̵������õ���Ƥߤޤ������ʴ���õ���Ƥ���ޤ����͡��ˤ��ޤ��㤬̵����Τξ�Φ/ȯ�ʤΥҥ�Ȥˤʤꤽ������Ƥϸ��Ĥ��ޤ�����
�ܲȥե�����ࡡRe: What/Where did you fly today? - Part 2 Postby AndersG
�ɤ����FlightGear�ǤϾ�ˤʤ�ޥƥꥢ�뤬ͥ�褵��Ƥ��ޤ��褦�ǡ��ɤ����Ƥ������ä��ִ֤˥ɥܥ�ȵޤ�����Ƥ��ޤ��褦�Ǥ���C172P�Ȥ��ǻ�ޤ�������������դˤ��ʤ������ٳ����������˥�������ᤷ���Ǥ���(�����ء�`)
�������ץե�����ν����Ǥ����������ޤ����Ѥ��������ʥ�κǸ�����줿�����ӤΥߥ���������ߤ����ʴ����Ǻ����ɤ����Ȼפ��ޤ�����QGIS �ȥݥ����Խ��פǸ����ݤ��ޤ���������ʥ����Ȥ�����ޤ�������QGIS�����Ѥ����ϼ�������������äȤ����ɤ�Ǥʤ��ƶ��̤Ǥ��������ͤˤʤ뤫�Ȼפ��ޤ����������ˤʤ�Τ����Խ������ݤ˲����ϿޤȤ������Ѥ���Ȥޤ������ϿޤΥ饤�������Ȥʤ�Τǡ����ִˤ�OpenStreetMap������������Ȼפ��ޤ�(�������������Ͽޤξ����Ĥ���ɬ�פ�����ޤ�)��
�Ǹ�������ʥ�Ǥ�����Terrain�����#5168938(�����ԡ�����ԡ�,#5168945,#5168946(���ܻԡ�������)�����äƤޤ��������줬������ڤ����äƤ��뤿��˴��������ʥ�������Ͽ����Ƥ����ʼ�ˡ��������ɤΰ����ǿ��פ��Ƥ��ޤ��ޤ����Ĥ��Ƥ�����ͳ��̵����оä��Ƥ��ޤä������ɤ����Ȼפ��ޤ����ɤ��Ǥ��礦����
����ȤҤȤޤ��δ����Ȥ��ƴ��������ʥ�Ȥ�����Ϥɤ����ޤ��礦����
�ޤ�hide��������������������ɤ��ڤ�Ƥ��ʤ��Τǡ��ޤ���������ޤ����饳���Ȥ����Ƥ��������ޤ���
��®����������ɤ����Ƥ������������˥���åפǿ�Φξ�ѵ���ͷ�Ф����Ƥ��������ޤ������������������桹̵���ΤǤ����Ǥ��͡�����å����������綶�⤢�ä���Ũ�Ǥ���
�ܲȥե�������Ʊ���褦���㤬̵������õ���Ƥߤޤ������ʴ���õ���Ƥ���ޤ����͡��ˤ��ޤ��㤬̵����Τξ�Φ/ȯ�ʤΥҥ�Ȥˤʤꤽ������Ƥϸ��Ĥ��ޤ�����
�ܲȥե�����ࡡRe: What/Where did you fly today? - Part 2 Postby AndersG
�ɤ����FlightGear�ǤϾ�ˤʤ�ޥƥꥢ�뤬ͥ�褵��Ƥ��ޤ��褦�ǡ��ɤ����Ƥ������ä��ִ֤˥ɥܥ�ȵޤ�����Ƥ��ޤ��褦�Ǥ���C172P�Ȥ��ǻ�ޤ�������������դˤ��ʤ������ٳ����������˥�������ᤷ���Ǥ���(�����ء�`)
�������ץե�����ν����Ǥ����������ޤ����Ѥ��������ʥ�κǸ�����줿�����ӤΥߥ���������ߤ����ʴ����Ǻ����ɤ����Ȼפ��ޤ�����QGIS �ȥݥ����Խ��פǸ����ݤ��ޤ���������ʥ����Ȥ�����ޤ�������QGIS�����Ѥ����ϼ�������������äȤ����ɤ�Ǥʤ��ƶ��̤Ǥ��������ͤˤʤ뤫�Ȼפ��ޤ����������ˤʤ�Τ����Խ������ݤ˲����ϿޤȤ������Ѥ���Ȥޤ������ϿޤΥ饤�������Ȥʤ�Τǡ����ִˤ�OpenStreetMap������������Ȼפ��ޤ�(�������������Ͽޤξ����Ĥ���ɬ�פ�����ޤ�)��
�Ǹ�������ʥ�Ǥ�����Terrain�����#5168938(�����ԡ�����ԡ�,#5168945,#5168946(���ܻԡ�������)�����äƤޤ��������줬������ڤ����äƤ��뤿��˴��������ʥ�������Ͽ����Ƥ����ʼ�ˡ��������ɤΰ����ǿ��פ��Ƥ��ޤ��ޤ����Ĥ��Ƥ�����ͳ��̵����оä��Ƥ��ޤä������ɤ����Ȼפ��ޤ����ɤ��Ǥ��礦����
����ȤҤȤޤ��δ����Ȥ��ƴ��������ʥ�Ȥ�����Ϥɤ����ޤ��礦����
�ޤ�hide��������������������ɤ��ڤ�Ƥ��ʤ��Τǡ��ޤ���������ޤ����饳���Ȥ����Ƥ��������ޤ���
--
OS:Win7 Pro 64bit
�� Ubuntu14.04LTS
FG version:Win7:3.4,2017.3.1
���������� Ubuntu:2016.1.1,2016.2.0
��ɼ��:19
ʿ����:4.74
hide
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
inomaty�����դϡ�hide�Ǥ���
�����ä��������ʥ�ڤ��߲����ä��ȤΤ��ȡ��ޤ������ε��Ťʥ��ɥХ�����ĺ���ޤ��ơ����Ѥ��꤬�Ȥ��������ޤ����������ǥ����ʥ�β����ǡ�Maishima2-fg-CustomScenery.zip�פ��äơ�JP���؎��ގŎَ��ގ��ݎێ��Ďޤ˥��åפ��ޤ������ʲ�������ɤäƴ�ñ�ˤ���𤷤ޤ���
������嵡�Υ���åץ������ˤĤ��ơ�
��FlightGear�ǥ���åפ��äƤ���������¾�ˤ⤪��줿�ΤǤ���!!�������Τäƴ��㤷�ޤ���(^^)�����������ǥ�Υ���åפϺ�ɸ������UFO��ȯ�����ޤ����������Ф˹Ҷ����ߤ��äˤʤ���������������Ĥ��ˤ������Ǥ��͡ġ����гѤ�פäƤߤ��Ȥ���6.1�٤��ꡢ���ܤΣ��٤���٤�Ⱦ����ޤǤ������Τˤ�äƤϡ��������٤γ������Ǥ�ȥ�֥뤬�����䤹���ʤ��礬����ޤ���
���ʿ���Φ�νִ֤ˤϡ��Τ����Τ��鵡�Τε�ư�����꤬����ޤ������Ҳ𤷤ޤ����褦�ˡ������ε���Ͼ���¤餲���¤�ǥ���å�������Ǥ��ޤ������������пʿ���˥ɥܥ��������Լ�����ư�����Τ�Τ��Ȥ���������ΤǤ��͡��ե����Ȥ����������⤤���֤ˡ��ܤ˸����ʤ�����ե����Ȥ����ؤΤ褦�ʤ�Τ�ץ�����ह��ʤɡ��٤��Τ褦�ʤ�Τ��פ��ơ����Τλ�����ȥ����뤹����̵�����ȡ������ȹͤ��Ƥ��ޤ����ޤ��¸����Ƥ��ޤ���
�����������ץե�����ν�����
�������Ӥβ�¤������ҥ�Ȥ������衢���줳���ޤ������ޤ������ʥ������Ӳ�äơ��Ҷ��̿��Ȥ����餫�˰ۤʤ����ܤΥƥ������㤬Ž���Ƥ�����ȡ������˻ȤäƤߤ����ƥ��������õ���Ф��ơ�QJIS�dz�ǧ��°���ơ��֥���Ƴƹ��ܤ���Ȥǽ�����ĤȤ�����ˡ�ǡ��ƥ���������ѹ����뤳�Ȥ��������ޤ������������٥����쥤��Ρ�ͻ�����ѹ�������դ��ʤ��褦�Ǥ����Τǡ��¼�Ū�ˤϡַ�礷�����ʳ�������ľ���ޤ��������楻���֤����ä��Τ�����Ϥ���ޤ���ˡ�
������ޤǤϡ��Ǥϱ�ư���ߤȸ���乹�Ϥ����ʤ����˻Գ��ϥƥ������㤬�и�����̴���Ǥ⥳��ƥ��֤��줬�Գ��Ϥ˲����Ƥ����ΤǤ��������줾����������������Ӥʤɤ��ѹ����뤳�Ȥ�����ơ��ºݤ����ʤΰ��ݤ��礭����Ť��ޤ�����Mateliral �ȥƥ���������б��ط��ϡ��ޤ�100��פ��̤�ˤϤʤ�ޤ�����Ʋ���������Ǥ���ĺ���ޤ����鹬���Ǥ����������ƹ����Ȥ������Ϥ����褿�Τǡ��礶�äѤ�¤��Ǥ������١����ܡ��륹����������ɲ�����ޤ�����
��OpenStreetMap �η��λ��Ǥ�������κ�Ȥˤϲ����ϻȤäƤ��ޤ��ݥꥴ����Խ��ϡ�ɬ�פ˱���ʬ���Ԥ������ǺѤޤ��ޤ�������ˡ�ϡ�GeoFabrik �������������ɤ���ƻϩ�ǡ�������ɸʪ�˻Ȥ�����¬�Ǽ꺢�ʥΡ���Ʊ�Τ����ʬ�䤹�롢�Ȥ�������Ū�ʤ�����Ǥ����Ρ��ɥġ����Ȥäơ���äȼ��ߤ˥ݥꥴ�����������ä����ꤹ�뤳�Ȥ��ޤ������������ϰϤ���ꤹ����ˡ�Ȥ�����������Ū�ʥƥ��˥å����褯ʬ���餺������ν���Ǥ���������ĺ������QGIS�����Ѥ����ϼ��������פ��乥�λ��ͽ�Ǥ��Τǡ����Ѥ��Ƥ��������Ȼפ��ޤ���
���������ʥ���ϰϤʤɡ�
��Terrain�ǡ����ˤĤ��ޤ��Ƥϡ��ޤä�������Ŧ���̤�Ǥ��ơ���5168938�ס�5168945�ס�5168946�פΣ��Ȥ����פǤ�����FlightGear�Υ����ʥ�ȿ����ǡ����Ǥϡ�������Ʊ�Τζ����������ʤ����ᡢ�������̤Ρ�5168937�ץ�����μ��Ϥˡ�;ʬ�˿����������������ƥ����ʥ�����������ݡ����㤤���褦�Ǥ��͡�����������ޤ���!!�������ͤǵ�ư��̤����꤬��ä��ޤ���(^^;)��
���ޤ����������ʥ�Ȥ�����Ǥ������������٤�̵����м���ΥС�����å��ˡ������ʥ��������ĺ���й����Ǥ���ñ�Ȥ��֤��Ƥ�����ꡢ¿���οͤ����Ѥ���ĺ�����Ȥ��Ǥ���Ȼפ��ޤ���
���䤬���襷���ʥ�˶����ɲä���Ȥ������פ����Ϥ��Ʒ�ʪ��¤�ꤿ���ʤä����Ϻ����Ʊ�ͤˡ���ꤢ���������룱��ʬ�����������ĺ���Ȥ�����ˡ�Ǥ���������Ȼפ��ޤ���
�����ä��������ʥ�ڤ��߲����ä��ȤΤ��ȡ��ޤ������ε��Ťʥ��ɥХ�����ĺ���ޤ��ơ����Ѥ��꤬�Ȥ��������ޤ����������ǥ����ʥ�β����ǡ�Maishima2-fg-CustomScenery.zip�פ��äơ�JP���؎��ގŎَ��ގ��ݎێ��Ďޤ˥��åפ��ޤ������ʲ�������ɤäƴ�ñ�ˤ���𤷤ޤ���
������嵡�Υ���åץ������ˤĤ��ơ�
��FlightGear�ǥ���åפ��äƤ���������¾�ˤ⤪��줿�ΤǤ���!!�������Τäƴ��㤷�ޤ���(^^)�����������ǥ�Υ���åפϺ�ɸ������UFO��ȯ�����ޤ����������Ф˹Ҷ����ߤ��äˤʤ���������������Ĥ��ˤ������Ǥ��͡ġ����гѤ�פäƤߤ��Ȥ���6.1�٤��ꡢ���ܤΣ��٤���٤�Ⱦ����ޤǤ������Τˤ�äƤϡ��������٤γ������Ǥ�ȥ�֥뤬�����䤹���ʤ��礬����ޤ���
���ʿ���Φ�νִ֤ˤϡ��Τ����Τ��鵡�Τε�ư�����꤬����ޤ������Ҳ𤷤ޤ����褦�ˡ������ε���Ͼ���¤餲���¤�ǥ���å�������Ǥ��ޤ������������пʿ���˥ɥܥ��������Լ�����ư�����Τ�Τ��Ȥ���������ΤǤ��͡��ե����Ȥ����������⤤���֤ˡ��ܤ˸����ʤ�����ե����Ȥ����ؤΤ褦�ʤ�Τ�ץ�����ह��ʤɡ��٤��Τ褦�ʤ�Τ��פ��ơ����Τλ�����ȥ����뤹����̵�����ȡ������ȹͤ��Ƥ��ޤ����ޤ��¸����Ƥ��ޤ���
�����������ץե�����ν�����
�������Ӥβ�¤������ҥ�Ȥ������衢���줳���ޤ������ޤ������ʥ������Ӳ�äơ��Ҷ��̿��Ȥ����餫�˰ۤʤ����ܤΥƥ������㤬Ž���Ƥ�����ȡ������˻ȤäƤߤ����ƥ��������õ���Ф��ơ�QJIS�dz�ǧ��°���ơ��֥���Ƴƹ��ܤ���Ȥǽ�����ĤȤ�����ˡ�ǡ��ƥ���������ѹ����뤳�Ȥ��������ޤ������������٥����쥤��Ρ�ͻ�����ѹ�������դ��ʤ��褦�Ǥ����Τǡ��¼�Ū�ˤϡַ�礷�����ʳ�������ľ���ޤ��������楻���֤����ä��Τ�����Ϥ���ޤ���ˡ�
������ޤǤϡ��Ǥϱ�ư���ߤȸ���乹�Ϥ����ʤ����˻Գ��ϥƥ������㤬�и�����̴���Ǥ⥳��ƥ��֤��줬�Գ��Ϥ˲����Ƥ����ΤǤ��������줾����������������Ӥʤɤ��ѹ����뤳�Ȥ�����ơ��ºݤ����ʤΰ��ݤ��礭����Ť��ޤ�����Mateliral �ȥƥ���������б��ط��ϡ��ޤ�100��פ��̤�ˤϤʤ�ޤ�����Ʋ���������Ǥ���ĺ���ޤ����鹬���Ǥ����������ƹ����Ȥ������Ϥ����褿�Τǡ��礶�äѤ�¤��Ǥ������١����ܡ��륹����������ɲ�����ޤ�����
��OpenStreetMap �η��λ��Ǥ�������κ�Ȥˤϲ����ϻȤäƤ��ޤ��ݥꥴ����Խ��ϡ�ɬ�פ˱���ʬ���Ԥ������ǺѤޤ��ޤ�������ˡ�ϡ�GeoFabrik �������������ɤ���ƻϩ�ǡ�������ɸʪ�˻Ȥ�����¬�Ǽ꺢�ʥΡ���Ʊ�Τ����ʬ�䤹�롢�Ȥ�������Ū�ʤ�����Ǥ����Ρ��ɥġ����Ȥäơ���äȼ��ߤ˥ݥꥴ�����������ä����ꤹ�뤳�Ȥ��ޤ������������ϰϤ���ꤹ����ˡ�Ȥ�����������Ū�ʥƥ��˥å����褯ʬ���餺������ν���Ǥ���������ĺ������QGIS�����Ѥ����ϼ��������פ��乥�λ��ͽ�Ǥ��Τǡ����Ѥ��Ƥ��������Ȼפ��ޤ���
���������ʥ���ϰϤʤɡ�
��Terrain�ǡ����ˤĤ��ޤ��Ƥϡ��ޤä�������Ŧ���̤�Ǥ��ơ���5168938�ס�5168945�ס�5168946�פΣ��Ȥ����פǤ�����FlightGear�Υ����ʥ�ȿ����ǡ����Ǥϡ�������Ʊ�Τζ����������ʤ����ᡢ�������̤Ρ�5168937�ץ�����μ��Ϥˡ�;ʬ�˿����������������ƥ����ʥ�����������ݡ����㤤���褦�Ǥ��͡�����������ޤ���!!�������ͤǵ�ư��̤����꤬��ä��ޤ���(^^;)��
���ޤ����������ʥ�Ȥ�����Ǥ������������٤�̵����м���ΥС�����å��ˡ������ʥ��������ĺ���й����Ǥ���ñ�Ȥ��֤��Ƥ�����ꡢ¿���οͤ����Ѥ���ĺ�����Ȥ��Ǥ���Ȼפ��ޤ���
���䤬���襷���ʥ�˶����ɲä���Ȥ������פ����Ϥ��Ʒ�ʪ��¤�ꤿ���ʤä����Ϻ����Ʊ�ͤˡ���ꤢ���������룱��ʬ�����������ĺ���Ȥ�����ˡ�Ǥ���������Ȼפ��ޤ���
��ɼ��:23
ʿ����:3.91
hide
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
hide�Ǥ�����嵡������åפ���ȯ�ʤ���ݡֿ�����ä��ִ֤˥ɥܥ�ȵޤ�����Ƥ��ޤ���������褹�뤿�ᡢ������ե����Ȥ����̡����̤Ȥ������ΰ��֤老�Ȥ�Ĵ�١��к�������ޤ�����
�����η�̡�DHC3���å����Ǥϡ֥ɥܥ���ݤ��ߤ�뤳�Ȥ�������������inomaty������Ƥ���줿C172P�Υ��Ȼ��Ρʶ��餯�ץ��ڥ�ο����ܿ��ˤϡ���ǰ�ʤ����μ�ˤ��館�ޤ���Ǥ������ʲ�����𤵤���ĺ���ޤ���
���ƥ��ȤǤϥܥ�Х�ǥ���415��DHC3��������172P������ǡ��ƥ�������̵�������ĥ�ǥ���Ѱա�AC3D���̾�ǥ����ȥե����Ȥ��������ˡ����줾���֤��ĤΥޡ�������������Ӥ��ޤ�����
���Σ������������Τϡ�
�����ܥ�Х�ǥ�������˳�餫�ʿʿ夬��ǽ
����DHC3���å�������������®���ʤ��ȡ��ɥܥ���ͤù���
����172P�������������⤤���٤ǥ���å��夹��
�ĤȤ����㤤�����뤿��Ǥ����ޡ������դ������Υ�ǥ�ϡ���Ʋ����֥ե����Ȳ��ɥƥ��ȡפκDz��ʤ˼����ޤ������̿��Ǥϡ�����������������ִݥޡ������ե����Ȥ��ܿ������Ĵݥޡ����ˤ��Ƥ��ޤ���
����YASim���Ρַ������к��ס�
���������������Ϥ�����⡢�ܼۤµ��̤����ο������ߤ����Ƥ��ޤ������äݤ��ܿ����ϡ��ե����Ȥ����Τ�������������ƥå���ʬ�������Ƹ����ηף�����ʬ�����Ƥ��뤳�Ȥ�ʬ����ޤ������������̤��Σ�������ɽ�����Ƥ���櫓�Ǥ��͡�
�������̤˸��ޤ��Ȳ�����ü�Υܥ�Х�ǥ����ϡ��ۥ�����١�������٤������ܿ����ȥ����������ι��㺹���������Ǥ������Τ����åפ����Ǥ��ݤ��̲᤹��ݤ�����Ѳ������ʤ������꤬�ɤ��ȹͤ����ޤ����ޤ����κ��������ܿ��������Ρ���������������ˤ��뤳�Ȥ��ÿ��ǡ��ʿ�������Τ�������˿��ª���ơ��Ρ������������濼�����߹���ʵ�������ƻ���Ƚ����ˤ��Ȥ��ɤ��Ǥ��ޤ���
�����˼̿����������DHC3������������������ϥե�������ü���ܿ����ȥ������������ۤ�Ʊ�����֤ˤ��ꡢ�⤵��������äƤ��ޤ������Τ��᳤�˾�������ȡ��ե����Ȥ��ޤ����Ϥ�ȯ�����ʤ������ˡ������䤬���̤�Ƨ��ȴ���Ƥ��ޤ��ޤ���inomaty����Τ���Ŧ�̤��FlightGear�ǤϾ�ˤʤ�ޥƥꥢ�뤬ͥ�褵��Ƥ��ޤ��פ��ᡢ����˱��줿����å�ɽ�̤ϡ����Τ�٤��뤳�Ȥ�����ޤ���ˡ������ǿ���ˤ���ե������ܿ����������褯���̤��������ꤷ���줺�ˡ֥ɥܥ���Ρפ�������櫓�Ǥ��͡�
�����Τε�ư��ܥ�Х�ǥ����˶�Ť��뤿�ᡢDHC3�Υ������������μФ�������ˡ������ʥե������ܿ����ʼ̿���Ǥϲ������ݥޡ����ˤ��ɲä��ޤ���������Ū�ˤϡ�Aircraft\dhc3\Systems\FDM\dhc3a-yasim.xml��248���ܰʹߤˡ�����ʸ��ä��Ƥ��ޤ���
<!-- safety float front L -->
<gear x="7.0" y="1.640" z="-2"
compression="1.5"
spring = "15"
sfric = "0.85"
dfric = "0.75"
ignored-by-solver="0"
on-water="1"
on-solid="0"
reduce-friction-by-extension="1.15"
speed-planing="25"
spring-factor-not-planing="0.25">
</gear>
<!-- safety float front R -->
<gear x="7.0" y="-1.640" z="-2"
compression="1.5"
spring = "15"
sfric = "0.85"
dfric = "0.75"
ignored-by-solver="0"
on-water="1"
on-solid="0"
reduce-friction-by-extension="1.15"
speed-planing="25"
spring-factor-not-planing="0.25">
</gear>
����̤��ɹ��ǡ����Τε�ư���礭���Ѳ����ޤ�������Ʋ����̿��κ��壳�礬����¤���Ρ֥ɥܥ���Ρס�����Σ��礬��¤���ư���ǡ��ޤ��������������Ʊ����ˡ�ǥ����ʤλ��Τ⡢�ɤ����ΤȻפ��ޤ�����
���������ʤ��桧
��������c172p�ϡ���ˤȤäƤ��ʤ���ʪ�Ǥ��������ε��Τϡ�������ե����Ȥ��̾��갷��<contact>�ǤϤʤ���<external_reactions>�Ȥ��������ǿ���ε�ư��ܤ������Ҥ��Ƥ��ޤ������Ƥ��Խ��Ǥ��ʤ����Ȱ�ֻפ��ޤ�����������館�ޤ���Ǥ�����
���Ȥʤ��DHC3Ʊ�͡��ե������ܿ������ɲä䡢�����������β�¤��ͤ��뤷���ʤ������Ǥ����Ȥ���������Ȥ����ʳ��Ȥ��ƥե������ܿ�����AC3D���̤˥ץ��åȤ����Ȥ������Ĵݥޡ����Ϥʤ����ե����Ȥ������ն�ǤϤʤ������̤��¤Ӥޤ�������Ʋ������Ȥ��������ˡ�c172p.xml�Υ�������������Ҥ�����ȥ�ȥ�ˡ�˴������ơ������VRP��Visual Reference Point����ϥե������ac�ե�����κ�ɸ�����κ��ˤ����������塢�����ΰ㤤�����դ����������ĤĤ��ʤΤǤ������ӡ�����������������ץ��åȤ��Ƥߤޤ���������Ϥ�ºݤȤϰ㤦���֤˽Фޤ����ʼ̿��ǤϾ�ά�ˡ�����ǤϿ����˥ե������ܿ��������ߤ��褦�ˤ⡢��ɸ����뤳�Ȥ�����ޤ���
�������ǥ��ץ��������Ѥ��褦�ȡ������ʤϿʿ夹��ݤɤ�����˥���å����Τ����ե饤�ȥ쥳�������Υ����������dz�ǧ���ޤ���������ȡ��ޤ��ե���ȥ�����������Ķ������ü���߹��ߡ��ե�������Ⱦ�Υ�������ʬ������å�ϩ�̤��ꡢȿư�ǥᥤ��������⤤�ơ����Τ����ˤĤ�Τ��ġĤȤ������ˤʤ�褦�Ǥ���
��������褹�뤿�ᡢ�ޤ�����åפ���ե����Ȥ����̤ˡ����������������ߤ��Ƥߤޤ������������ץ������Τɤ�����̷�⤫̵��������餷�������ץ���ǵ��Τ�ư����ȡ��ᥤ�������̤ˤ�����ǥե����Ȥ�ʢ�ꡢ������Ϥ�夲�Ƥ⥿�������뤳�Ȥ�����ޤ��ե����ȴط���������ͤ줳���Ѥ��Ƥ����Ǥ�����
�����ؼ��ʤȤ��ơ��������ߤ�����˥ե�������ü�ˤ��륮���ΰ��֤�30������ۤɸ���˲����ơ��ե�������Ⱦ��٤��褦�Ȥ��ޤ��������ʤ������̤�̵�������Τϲ�¤���Ȥޤä���Ʊ���������֤ǡ��ե����Ȥ��ɥ֥��������ޤ�����
�������Ǥϡ�c172p��åפ���μ¤�ȯ�ʤ��������ʤ顢����å����̵���ˤ��뤷���ʤ��褦�Ǥ�����FlightGear�������Ǥ����Ѥ�������¿���Ǥ�������������ˡ��ɤ����ǰ�ʤ��äǤ���
��12��15���뵭�������ᡧ
����ʸ��Ⱦ�ˤ���֥���åפ���ե����Ȥ����̤ˡ����������������ߤ��Ƥߤޤ����פ���ʬ��ʬ����ˤ����Τ������ޤ���
�����ξ�硢���������ߤ����������κ�ɸ����ȵ��뤳�Ȥ�����Ǥ��Τǡ��ǥե���Ȥ� c172p.xml�˽��ޤ�Ƥ�������Υӡ��������ʺ��ե����Ȥ���˵�� LFFloatGear �� LMFloatGear�ˤκ�ɸ����������Ū�˻��Ф��ư��ַ�ᤷ�ޤ�����
��Ʊ�ͤˡ֥������ߤ�����˥ե�������ü�ˤ��륮���ΰ��֤�30������ۤɸ���˲����פ��¤�⡢����ñ���X��ɸ�ο��ͤ��ѹ����ޤ�����
�����η�̡�DHC3���å����Ǥϡ֥ɥܥ���ݤ��ߤ�뤳�Ȥ�������������inomaty������Ƥ���줿C172P�Υ��Ȼ��Ρʶ��餯�ץ��ڥ�ο����ܿ��ˤϡ���ǰ�ʤ����μ�ˤ��館�ޤ���Ǥ������ʲ�����𤵤���ĺ���ޤ���
���ƥ��ȤǤϥܥ�Х�ǥ���415��DHC3��������172P������ǡ��ƥ�������̵�������ĥ�ǥ���Ѱա�AC3D���̾�ǥ����ȥե����Ȥ��������ˡ����줾���֤��ĤΥޡ�������������Ӥ��ޤ�����
���Σ������������Τϡ�
�����ܥ�Х�ǥ�������˳�餫�ʿʿ夬��ǽ
����DHC3���å�������������®���ʤ��ȡ��ɥܥ���ͤù���
����172P�������������⤤���٤ǥ���å��夹��
�ĤȤ����㤤�����뤿��Ǥ����ޡ������դ������Υ�ǥ�ϡ���Ʋ����֥ե����Ȳ��ɥƥ��ȡפκDz��ʤ˼����ޤ������̿��Ǥϡ�����������������ִݥޡ������ե����Ȥ��ܿ������Ĵݥޡ����ˤ��Ƥ��ޤ���
����YASim���Ρַ������к��ס�
���������������Ϥ�����⡢�ܼۤµ��̤����ο������ߤ����Ƥ��ޤ������äݤ��ܿ����ϡ��ե����Ȥ����Τ�������������ƥå���ʬ�������Ƹ����ηף�����ʬ�����Ƥ��뤳�Ȥ�ʬ����ޤ������������̤��Σ�������ɽ�����Ƥ���櫓�Ǥ��͡�
�������̤˸��ޤ��Ȳ�����ü�Υܥ�Х�ǥ����ϡ��ۥ�����١�������٤������ܿ����ȥ����������ι��㺹���������Ǥ������Τ����åפ����Ǥ��ݤ��̲᤹��ݤ�����Ѳ������ʤ������꤬�ɤ��ȹͤ����ޤ����ޤ����κ��������ܿ��������Ρ���������������ˤ��뤳�Ȥ��ÿ��ǡ��ʿ�������Τ�������˿��ª���ơ��Ρ������������濼�����߹���ʵ�������ƻ���Ƚ����ˤ��Ȥ��ɤ��Ǥ��ޤ���
�����˼̿����������DHC3������������������ϥե�������ü���ܿ����ȥ������������ۤ�Ʊ�����֤ˤ��ꡢ�⤵��������äƤ��ޤ������Τ��᳤�˾�������ȡ��ե����Ȥ��ޤ����Ϥ�ȯ�����ʤ������ˡ������䤬���̤�Ƨ��ȴ���Ƥ��ޤ��ޤ���inomaty����Τ���Ŧ�̤��FlightGear�ǤϾ�ˤʤ�ޥƥꥢ�뤬ͥ�褵��Ƥ��ޤ��פ��ᡢ����˱��줿����å�ɽ�̤ϡ����Τ�٤��뤳�Ȥ�����ޤ���ˡ������ǿ���ˤ���ե������ܿ����������褯���̤��������ꤷ���줺�ˡ֥ɥܥ���Ρפ�������櫓�Ǥ��͡�
�����Τε�ư��ܥ�Х�ǥ����˶�Ť��뤿�ᡢDHC3�Υ������������μФ�������ˡ������ʥե������ܿ����ʼ̿���Ǥϲ������ݥޡ����ˤ��ɲä��ޤ���������Ū�ˤϡ�Aircraft\dhc3\Systems\FDM\dhc3a-yasim.xml��248���ܰʹߤˡ�����ʸ��ä��Ƥ��ޤ���
<!-- safety float front L -->
<gear x="7.0" y="1.640" z="-2"
compression="1.5"
spring = "15"
sfric = "0.85"
dfric = "0.75"
ignored-by-solver="0"
on-water="1"
on-solid="0"
reduce-friction-by-extension="1.15"
speed-planing="25"
spring-factor-not-planing="0.25">
</gear>
<!-- safety float front R -->
<gear x="7.0" y="-1.640" z="-2"
compression="1.5"
spring = "15"
sfric = "0.85"
dfric = "0.75"
ignored-by-solver="0"
on-water="1"
on-solid="0"
reduce-friction-by-extension="1.15"
speed-planing="25"
spring-factor-not-planing="0.25">
</gear>
����̤��ɹ��ǡ����Τε�ư���礭���Ѳ����ޤ�������Ʋ����̿��κ��壳�礬����¤���Ρ֥ɥܥ���Ρס�����Σ��礬��¤���ư���ǡ��ޤ��������������Ʊ����ˡ�ǥ����ʤλ��Τ⡢�ɤ����ΤȻפ��ޤ�����
���������ʤ��桧
��������c172p�ϡ���ˤȤäƤ��ʤ���ʪ�Ǥ��������ε��Τϡ�������ե����Ȥ��̾��갷��<contact>�ǤϤʤ���<external_reactions>�Ȥ��������ǿ���ε�ư��ܤ������Ҥ��Ƥ��ޤ������Ƥ��Խ��Ǥ��ʤ����Ȱ�ֻפ��ޤ�����������館�ޤ���Ǥ�����
���Ȥʤ��DHC3Ʊ�͡��ե������ܿ������ɲä䡢�����������β�¤��ͤ��뤷���ʤ������Ǥ����Ȥ���������Ȥ����ʳ��Ȥ��ƥե������ܿ�����AC3D���̤˥ץ��åȤ����Ȥ������Ĵݥޡ����Ϥʤ����ե����Ȥ������ն�ǤϤʤ������̤��¤Ӥޤ�������Ʋ������Ȥ��������ˡ�c172p.xml�Υ�������������Ҥ�����ȥ�ȥ�ˡ�˴������ơ������VRP��Visual Reference Point����ϥե������ac�ե�����κ�ɸ�����κ��ˤ����������塢�����ΰ㤤�����դ����������ĤĤ��ʤΤǤ������ӡ�����������������ץ��åȤ��Ƥߤޤ���������Ϥ�ºݤȤϰ㤦���֤˽Фޤ����ʼ̿��ǤϾ�ά�ˡ�����ǤϿ����˥ե������ܿ��������ߤ��褦�ˤ⡢��ɸ����뤳�Ȥ�����ޤ���
�������ǥ��ץ��������Ѥ��褦�ȡ������ʤϿʿ夹��ݤɤ�����˥���å����Τ����ե饤�ȥ쥳�������Υ����������dz�ǧ���ޤ���������ȡ��ޤ��ե���ȥ�����������Ķ������ü���߹��ߡ��ե�������Ⱦ�Υ�������ʬ������å�ϩ�̤��ꡢȿư�ǥᥤ��������⤤�ơ����Τ����ˤĤ�Τ��ġĤȤ������ˤʤ�褦�Ǥ���
��������褹�뤿�ᡢ�ޤ�����åפ���ե����Ȥ����̤ˡ����������������ߤ��Ƥߤޤ������������ץ������Τɤ�����̷�⤫̵��������餷�������ץ���ǵ��Τ�ư����ȡ��ᥤ�������̤ˤ�����ǥե����Ȥ�ʢ�ꡢ������Ϥ�夲�Ƥ⥿�������뤳�Ȥ�����ޤ��ե����ȴط���������ͤ줳���Ѥ��Ƥ����Ǥ�����
�����ؼ��ʤȤ��ơ��������ߤ�����˥ե�������ü�ˤ��륮���ΰ��֤�30������ۤɸ���˲����ơ��ե�������Ⱦ��٤��褦�Ȥ��ޤ��������ʤ������̤�̵�������Τϲ�¤���Ȥޤä���Ʊ���������֤ǡ��ե����Ȥ��ɥ֥��������ޤ�����
�������Ǥϡ�c172p��åפ���μ¤�ȯ�ʤ��������ʤ顢����å����̵���ˤ��뤷���ʤ��褦�Ǥ�����FlightGear�������Ǥ����Ѥ�������¿���Ǥ�������������ˡ��ɤ����ǰ�ʤ��äǤ���
��12��15���뵭�������ᡧ
����ʸ��Ⱦ�ˤ���֥���åפ���ե����Ȥ����̤ˡ����������������ߤ��Ƥߤޤ����פ���ʬ��ʬ����ˤ����Τ������ޤ���
�����ξ�硢���������ߤ����������κ�ɸ����ȵ��뤳�Ȥ�����Ǥ��Τǡ��ǥե���Ȥ� c172p.xml�˽��ޤ�Ƥ�������Υӡ��������ʺ��ե����Ȥ���˵�� LFFloatGear �� LMFloatGear�ˤκ�ɸ����������Ū�˻��Ф��ư��ַ�ᤷ�ޤ�����
��Ʊ�ͤˡ֥������ߤ�����˥ե�������ü�ˤ��륮���ΰ��֤�30������ۤɸ���˲����פ��¤�⡢����ñ���X��ɸ�ο��ͤ��ѹ����ޤ�����
��ɼ��:20
ʿ����:5.50
inomaty
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
inomaty�Ǥ�����̵�������Ƥ���ޤ���
�Ȥꤢ�������������줿�ǤȤ��ƥ������ޤ�����
����ȤĤ��Ǥˡ�������פ����������ߥ�ºݤΤ�Τ˹�碌�Ƥߤޤ����������ȥ�����������˺��Ƥ��ޤä��Τ�ʬ����Ť餤���⤷��ޤ��������Ƥ��̤�ˡ���٥��ȥ�κ�ɸ��animation��flash��axis�ι�������Ȥ����Τ��ݥ���ȤǤ��礦���͡�����ʴ����Ǥ�������Ǥ��礦����
���νդ�����˰�ð�����Υ����ߥʥ�Ȥ����������褦�ȴ�ĥ�äƤߤޤ��������ޤ�Ⱦʬ�ۤɤǤ���(�ե����Ȥγ�ǧ���ʤ�Ǥʤ��Ƥ��ߤޤ���Systems�ե��������c172p-hydrodynamics.xml���ݥ���ȤΤ褦�ʵ��⤷�ޤ����褯ʬ���äƤޤ��פ��ڤäƱѸ�ե������ǰ�Ϣ��ή����������ޤ��礦����������)


�������оΤȤ����櫓�ǤϤʤ��ΤǤޤ����֤����ꤽ���Ǥ���MRO Japan�ΰ�ž�ޤǤˤϴ֤˹�碌�����Ȼפ��ޤ����ɤ��ʤ뤳�Ȥ���������
�Ȥꤢ�������������줿�ǤȤ��ƥ������ޤ�����
����ȤĤ��Ǥˡ�������פ����������ߥ�ºݤΤ�Τ˹�碌�Ƥߤޤ����������ȥ�����������˺��Ƥ��ޤä��Τ�ʬ����Ť餤���⤷��ޤ��������Ƥ��̤�ˡ���٥��ȥ�κ�ɸ��animation��flash��axis�ι�������Ȥ����Τ��ݥ���ȤǤ��礦���͡�����ʴ����Ǥ�������Ǥ��礦����
���νդ�����˰�ð�����Υ����ߥʥ�Ȥ����������褦�ȴ�ĥ�äƤߤޤ��������ޤ�Ⱦʬ�ۤɤǤ���(�ե����Ȥγ�ǧ���ʤ�Ǥʤ��Ƥ��ߤޤ���Systems�ե��������c172p-hydrodynamics.xml���ݥ���ȤΤ褦�ʵ��⤷�ޤ����褯ʬ���äƤޤ��פ��ڤäƱѸ�ե������ǰ�Ϣ��ή����������ޤ��礦����������)


�������оΤȤ����櫓�ǤϤʤ��ΤǤޤ����֤����ꤽ���Ǥ���MRO Japan�ΰ�ž�ޤǤˤϴ֤˹�碌�����Ȼפ��ޤ����ɤ��ʤ뤳�Ȥ���������
--
OS:Win7 Pro 64bit
�� Ubuntu14.04LTS
FG version:Win7:3.4,2017.3.1
���������� Ubuntu:2016.1.1,2016.2.0
��ɼ��:18
ʿ����:4.44
hide
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
inomaty����̵�������Ƥ���ޤ���hide�Ǥ���
�����������ʥ���������Dz������ޤ��ơ����Ѥ��꤬�Ȥ��������ޤ�����
������η�Ǥ�����3����äƵ٤ߡ��ȸ����Τ���ˤϼ¸�����ʤ��ä��ΤǴ�ư���ޤ������������ϡ��ޤä���������������Ȼפ��ޤ����ʤ��������Ҥ���Ȥ����ʤ�Τ�����Ϥޤ����߹��᤺�ˤ��ޤ���������������ꥢ��˺���ǽ����������ޤ���!!
������������ǰ�ʤΤϡ��إ�ݡ����ƤΡ�����̹�������פȡ��ޥ����������������ü�ˤ�������������������פ���Ʊ���������ˤʤäƤ��뤳�ȤǤ�������ϼ¤ϡ����������㤦�ΤǤ���
�������إ�ݡ����ơ�����̹�������ַ����ָ� ��12�ä�3�����ס�
�������ޥ��¦�ϡ�����������������ñ���ָ�����4�ä�1�����ס�
�ĤȤʤäƤ���ޤ��ơ��ޥ�ʤ�����������ϡ������̤�1ȯ��������Ǥ�������ä��ΤǤ�����������ץ������κ��ʬ���˼��Ԥ��������ǡ�1�Ĥ�����ե������2��������֤��Ƹ��ⲽ���Ƥ��ޤ��ޤ�������ʬ����ˤ���������ǿ���������ޤ����(^^;)��
����ð�����μ̿����Ҹ����������ʾ�ν���Ǥ��˶ä��Ƥ��ޤ������������˳ڤ��ߤǤ��������ʤΥե����Ȥη�ϡ���⤽�ΤޤޤˤʤäƤ���ޤ�����FlightGear�Υ����ʥ2.0�����ˤϡ��Τ�¾�ˤ⾮���Ϥʥ���åץ�����������ޤ������������դǤ��ä��ץ�ˤ��Ƥߤ�ΤϤ��������ǥ����Ǥ��͡�
�����������ʥ���������Dz������ޤ��ơ����Ѥ��꤬�Ȥ��������ޤ�����
������η�Ǥ�����3����äƵ٤ߡ��ȸ����Τ���ˤϼ¸�����ʤ��ä��ΤǴ�ư���ޤ������������ϡ��ޤä���������������Ȼפ��ޤ����ʤ��������Ҥ���Ȥ����ʤ�Τ�����Ϥޤ����߹��᤺�ˤ��ޤ���������������ꥢ��˺���ǽ����������ޤ���!!
������������ǰ�ʤΤϡ��إ�ݡ����ƤΡ�����̹�������פȡ��ޥ����������������ü�ˤ�������������������פ���Ʊ���������ˤʤäƤ��뤳�ȤǤ�������ϼ¤ϡ����������㤦�ΤǤ���
�������إ�ݡ����ơ�����̹�������ַ����ָ� ��12�ä�3�����ס�
�������ޥ��¦�ϡ�����������������ñ���ָ�����4�ä�1�����ס�
�ĤȤʤäƤ���ޤ��ơ��ޥ�ʤ�����������ϡ������̤�1ȯ��������Ǥ�������ä��ΤǤ�����������ץ������κ��ʬ���˼��Ԥ��������ǡ�1�Ĥ�����ե������2��������֤��Ƹ��ⲽ���Ƥ��ޤ��ޤ�������ʬ����ˤ���������ǿ���������ޤ����(^^;)��
����ð�����μ̿����Ҹ����������ʾ�ν���Ǥ��˶ä��Ƥ��ޤ������������˳ڤ��ߤǤ��������ʤΥե����Ȥη�ϡ���⤽�ΤޤޤˤʤäƤ���ޤ�����FlightGear�Υ����ʥ2.0�����ˤϡ��Τ�¾�ˤ⾮���Ϥʥ���åץ�����������ޤ������������դǤ��ä��ץ�ˤ��Ƥߤ�ΤϤ��������ǥ����Ǥ��͡�
��ɼ��:10
ʿ����:5.00
inomaty
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
 ��ƿ�: 164
��ƿ�: 164
����Ф�ϡ�inomaty�Ǥ���
flash���˥������axis�����꤬ʬ����Ť餤�ȤΤ��ȤǤ��Τǡ���ʤ�β���Τ��ޤ���
���ʤߤ�wiki�ε��Ҥϥ������̤�Ǥ���
http://wiki.flightgear.org/Howto:Animate_models#Flash

�ޤκ�¦��Maishima�����ʥ�����äƤ���hide�����줿RedLightHouseɽ���Ƥ��ޤ���3�������ȿޤ���Τ����Ѥ����Ǥ����Τ�2�����Ǽ��餷�ޤ���������Ĺ�������������������������ˡ���٥��ȥ�(�礭����1)�Ǥ���ˡ���٥��ȥ��(x,y)=(0,-1)�Ǥ���
��ö����������ž���ʤ�(rotation���˥�����̵������)�ȹͤ��ޤ��礦�����κ�ɸ��flash���˥������axis�����˽�RedLightHouse��̵��ž�ξ��֤�����(y�������̡�x��������)����ȡ����������鸫�ƻ���������ˤ���Ȥ�������������ɽ�����졢¾�ΰ��֤Ǥϸ����ʤ��ʤ�ޤ���
³���ƾ夫�鸫��60deg����������ײ�������˲�ž�����Τ��ޤα�¦�Ǥ���ˡ���٥��ȥ��(x,y)=(sin(-120deg),cos(-120deg))��(-0.8660,-0.5)�Ȥʤ�ޤ�������Ʊ��rotation���˥�����̵����y��������x���������ξ��֤����֤���ȹͤ���ȡ��������Ͽ���ǤϤʤ������60����¦�ظ����ä����֤���Ǥ褦�䤯������褦�ˤʤ�ޤ���
��Σ��Ĥ���Τ������֤Ǿ夫�鸫�ƻ��������˲�ž�����ޤ���y������������鸫��кǽ��60deg��ž���������������ơ�³���Ʋ�ž��0deg(�ǽ����)��������Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
�⤦1����������Ϲ��˻���������60deg�Ƥ���ޤ��Τǡ�axis�κ�ɸ��(x,y)��(-0.8660,0.5)�Ȥʤ�ޤ���
����ʤȤ����Ǥ������Ǥ��礦����
���Ĥ�����������ѥ�����⽤�����ޤ����������ʥ�ե�����������Ĥ����äƼ��㤨�Ƥ����ǽ���⤢��ޤ��ΤǤ���ǧ���ꤤ���ޤ���
flash���˥������axis�����꤬ʬ����Ť餤�ȤΤ��ȤǤ��Τǡ���ʤ�β���Τ��ޤ���
���ʤߤ�wiki�ε��Ҥϥ������̤�Ǥ���
http://wiki.flightgear.org/Howto:Animate_models#Flash

�ޤκ�¦��Maishima�����ʥ�����äƤ���hide�����줿RedLightHouseɽ���Ƥ��ޤ���3�������ȿޤ���Τ����Ѥ����Ǥ����Τ�2�����Ǽ��餷�ޤ���������Ĺ�������������������������ˡ���٥��ȥ�(�礭����1)�Ǥ���ˡ���٥��ȥ��(x,y)=(0,-1)�Ǥ���
��ö����������ž���ʤ�(rotation���˥�����̵������)�ȹͤ��ޤ��礦�����κ�ɸ��flash���˥������axis�����˽�RedLightHouse��̵��ž�ξ��֤�����(y�������̡�x��������)����ȡ����������鸫�ƻ���������ˤ���Ȥ�������������ɽ�����졢¾�ΰ��֤Ǥϸ����ʤ��ʤ�ޤ���
³���ƾ夫�鸫��60deg����������ײ�������˲�ž�����Τ��ޤα�¦�Ǥ���ˡ���٥��ȥ��(x,y)=(sin(-120deg),cos(-120deg))��(-0.8660,-0.5)�Ȥʤ�ޤ�������Ʊ��rotation���˥�����̵����y��������x���������ξ��֤����֤���ȹͤ���ȡ��������Ͽ���ǤϤʤ������60����¦�ظ����ä����֤���Ǥ褦�䤯������褦�ˤʤ�ޤ���
��Σ��Ĥ���Τ������֤Ǿ夫�鸫�ƻ��������˲�ž�����ޤ���y������������鸫��кǽ��60deg��ž���������������ơ�³���Ʋ�ž��0deg(�ǽ����)��������Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
�⤦1����������Ϲ��˻���������60deg�Ƥ���ޤ��Τǡ�axis�κ�ɸ��(x,y)��(-0.8660,0.5)�Ȥʤ�ޤ���
����ʤȤ����Ǥ������Ǥ��礦����
���Ĥ�����������ѥ�����⽤�����ޤ����������ʥ�ե�����������Ĥ����äƼ��㤨�Ƥ����ǽ���⤢��ޤ��ΤǤ���ǧ���ꤤ���ޤ���
--
OS:Win7 Pro 64bit
�� Ubuntu14.04LTS
FG version:Win7:3.4,2017.3.1
���������� Ubuntu:2016.1.1,2016.2.0
��ɼ��:15
ʿ����:5.33
hide
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
 �サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
�サ��: ʼ�˸�
��ƿ�: 650
���ʤ���ۤɡ�axis�θ����Ϥ����������Ȥ��ä��ΤǤ���!!��ʿ�̾�������������ˡ���٥��ȥ�ʤĤޤ�ϸ����ˤ������Ƥ��������ɸ�����Ȥ���ʬ��ʬ�ƻ��ꤹ����ɤ��ä��ΤǤ��͡�
���䤬��������ȯ����������ϡ�ȯ���̤ϣ��礢��ޤ����������פ��Ф��֤������Ʊ�������Ǥ��������äơ��������Τ�����ž���뤿�Ӥˣ���ȯ�����ʤ��ä��ΤǤ�����ʬ����䤹�������������Ѥ��꤬�Ȥ��������ޤ���!! ���ޤ����鿽���夲�ޤ���
��10��������������յ��������ä������ɤ��Ʋ����ä������ʥ�����������ɤ�����ĺ���ޤ����������ȯ���ϴ����Ǥ�����
���䤬��������ȯ����������ϡ�ȯ���̤ϣ��礢��ޤ����������פ��Ф��֤������Ʊ�������Ǥ��������äơ��������Τ�����ž���뤿�Ӥˣ���ȯ�����ʤ��ä��ΤǤ�����ʬ����䤹�������������Ѥ��꤬�Ȥ��������ޤ���!! ���ޤ����鿽���夲�ޤ���
��10��������������յ��������ä������ɤ��Ʋ����ä������ʥ�����������ɤ�����ĺ���ޤ����������ȯ���ϴ����Ǥ�����
��ɼ��:13
ʿ����:4.62







